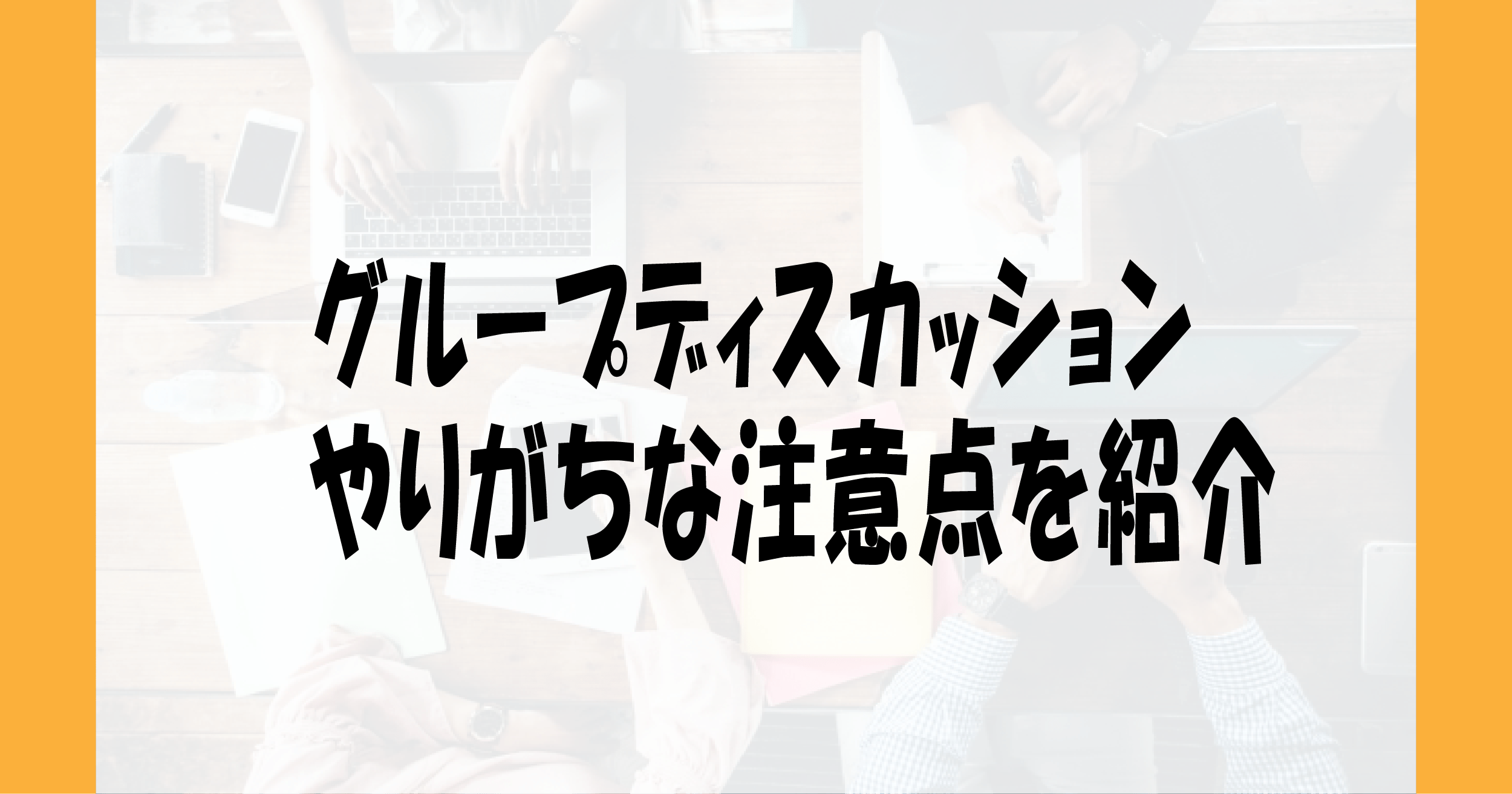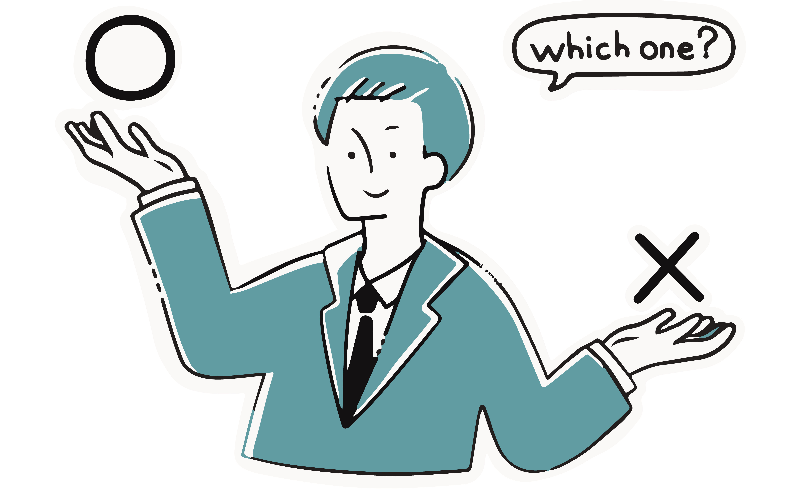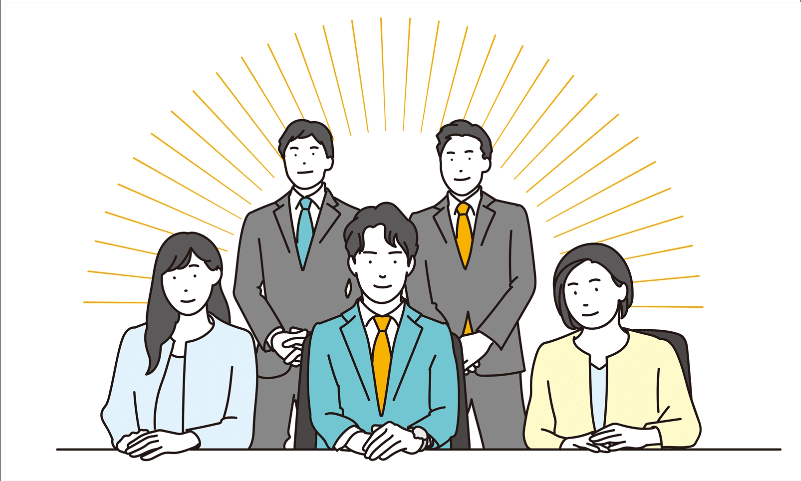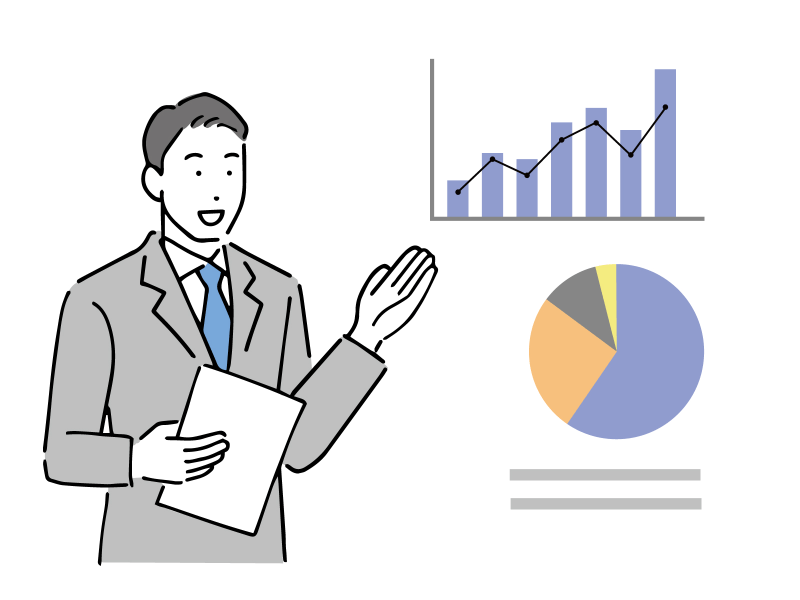グループディスカッションで注意しなければならないところは結構あります。それも皆さんが気づかずにやってしまっていることです。
その注意点さえ無くしてしまえば、減点はなくなるため選考にとても通りやすくなります。
なので今回はグループディスカッションの注意点10選を紹介していこうと思います。
グループディスカッション注意点10選
喋りすぎる
最初の注意点はしゃべりすぎないことです。特にコミュニケーション力が高いと自負している学生は要注意です。
発信力はとても重要な評価項目ではありますが、しゃべりすぎはマイナスポイントです。
しゃべりすぎることのマイナス点は、他のメンバーの話す機会を失わせてしまうことと自分本位になることで協調性の欠如という点でマイナスになります。
発言がわかりづらい
発言には量と質の観点があります。どんなにたくさん話をしても相手や観察者にその意思が伝わらないと意味がありません。
発言がわかりにくい人の特徴は、わかりやすい発言の仕方で話をしていません。意見の趣旨(結論)+理由+理由の補足というのが最もわかりやすい発言方法ですが、理由がないもしくは不十分というケースが多く見受けられます。
そして、理由の補足の部分と理由との間に一貫性が無い場合です。
最悪なのは結論と理由に論理的なつながりがないことです。このような話し方では、グループメンバーに伝わらないばかりか、採点者にその意図が伝わらないのでマイナス評価になります。
怒る
議論は平常心を保つことが重要です。喜怒哀楽は重要ですが、その中でも怒るというのは避けねばなりません。
怒ることのマイナス点は、ディスカッションの雰囲気が悪くなることです。雰囲気が悪くなると良い意見が出ません。
そして、怒るというのは他人に対するいら立ちを表しているのですから、協同作業をうまく進められないと観察者に伝えているようなものです。
他人を批判する
怒るのと同じように他人を批判することもいけません。グループディスカッションは全員参加の合意形成が重要です。批判という好意は、この全員参加、合意形成を妨げてしまいます。
批判に対しての基本的な対応は反発、もしくは無視、逃避です。
反発が起きれば、グループの雰囲気が一気に悪くなります。そして逃避する人が出れば全員参加が達成できませんから、批判ではなく、建設的対応を心がけましょう。
意見に反対するのは全然ok
しかし、反対意見を言ってはいけないわけではありません。
むしろ、全ての意見を反対しないで盛り込んでいくと結論が意味不明になります。
最近は反対意見を言ってはいけないと思う学生がすべての意見を取り入れてしまうケースも見受けられます。これでは結論が意味不明になります。
反対意見を言うときは言い方に注意すべきなのです。
最初は意見を言ってくれたことに感謝し、同意したうえで自分の意見を添えることです。いわゆるYES-BUT法です。
最初は同意して反対意見を言いましょう。これも訓練しないとうまく言えませんから日頃からこの話法を使ってみましょう。
たった1日であなたのグルディス対策を完結させます

グループディスカッションに合格するには絶対に実践経験が必要です。
「出会いの場」に参加すると、以下のメリットがあります。
・1日15分×4回の実践による圧倒的練習量
・実際の人事の採点であなたの得意不得意と順位が分かる
・一度に最大14社と出会え、直接企業の本選考に進める
グルディス対策をしたい&1日で就活を大幅に進めたいという方はぜひご参加ください!
雰囲気を悪くする
グループディスカッションにおいて雰囲気は重要です。雰囲気によって場が盛り上がったり、暗くなったりします。
雰囲気を悪くする行為は、取り組み姿勢です。腕を組んだりして拒否のポーズをとったりしていませんか。
あなたの姿勢や顔の表情が相手に心理的影響を与えます。そして話し方もあります。攻撃的な話し方を辞めて、好意的で友好的な話し方に努めましょう。
自分の意見を曲げない
自分の意見を曲げないで主張し続けるのも全体の大きな影響を及ぼします。グループディスカッションの目的を思い返しましょう。
意見で勝つことではありません。グループで全員参加して合意形成を図ることです。グループディスカッションには絶対的な正解があるわけではありません。
合意形成するプロセスが重要です。意見を曲げないことで観察者は協調性が無いと判定します。協調性は重要な要素です。
時間を守る
グループディスカッションは決められた時間で結論を出さないといけません。時間内で結論に至らないと企業によっては引く評価をするケースもあります。
時間内で合意をすることは必須条件です。そのために議論する時間配分をしっかり決めて計画通りに進めることが重要です。
その為にもきちんとタイムキーパーを置いて時間を管理しながら進めることが重要です。
遠慮しすぎる
最近の学生の傾向は遠慮して思ったことを発言しないケースが多いことです。グループ全体の議論の活性化につながらないだけでなく、遠慮しすぎるとあなた個人の評価が下がります。
遠慮する人は発言のタイミングを逸してしまうケースとアイデアが浮かばないといった二つのケースがあります。
タイミングは人の意見の終わりに同意の言葉をはさんで意見を言うのが入りやすいです。
「なるほど、いい意見だと思います。私は○○」というように入るやり方が効果的ですから試してみましょう。
アイデアを出すのが苦手な人は、普段からアイデアを出す練習をして本番に備えましょう。アイデアが出ない場合は、5W1H法を活用しましょう。グルディスの問題は5W1Hの全ての情報がないことです。
自分でない情報を積み上げることで新たなアイデアが出ます。詳しくはアイデアの出し方の記事を読んで見てください。
適切に話を振る
協調性をアピールするために司会者のように振る舞う人がいます。「○○さんはどう思う」「○○さん、対案はありますか」このような振りです。
相手がしゃべりたがっているみたいに行動を観察しているのならばよいのですが、行動を観察しないで適当に意見を求めたり、発言しにくい振り方では振られた相手は対応が取れません。
話しやすい振りと話しにくい振りを普段から意識しておきましょう。
印象が悪くなる癖に注意する
印象が悪くなる癖はいくつかあります。いくつかの癖を挙げます。該当する癖がある人は早期から直すようにしましょう。
・腕を組む
腕を組むと拒否のポーズとなります。拒否のポーズは相手に話をさせにくくさせてしまうので普段から注意が必要です。
・貧乏ゆすり
貧乏ゆすりの癖は周りに迷惑をかけてしまいます。日常生活で直す努力が必要です。
・椅子で胡坐をかく
リラックスにも限度というものがありますから、特に自宅ではありませんから、姿勢も見られていることを普段から意識しましょう。
オンラインのグループディスカッションばかり実施しているとその癖が抜けません。対面でのグループディスカッションを意識しましょう。
・なんでも相槌を打つを打つ
相槌を打つことはとても良いことですが度を超すと気になってしまいます。
相槌の声が大きすぎないようにしましょう。そして、どんな意見でも相槌を打つと安易にうなづいていると思われます。
グループディスカッションでどんな人が受かるにか気になりませんか?累計7万人の参加者の中で受かる人の特徴があることが気づいたので、合わせてご覧ください。
まとめ
今日はグループディスカッションする上での注意点を10個上げました。
知らず知らずに出る癖もありますが、早いうちから直しておきましょう。
特に自己主張が強い傾向がある学生はグループディカッションを練習して慣れておく必要があります。採用におけるグループディスカッションは見られてる選考です。
オンラインは見られてる意識が低いですから、対面で訓練しておかないと思わぬ癖が出てしまいます。
この記事と併せて読みたいグループディスカッションの厳選記事
・グループディスカッションの絶対に受かりたい人におすすめの記事
・グループディスカッションで話せない人におすすめの記事