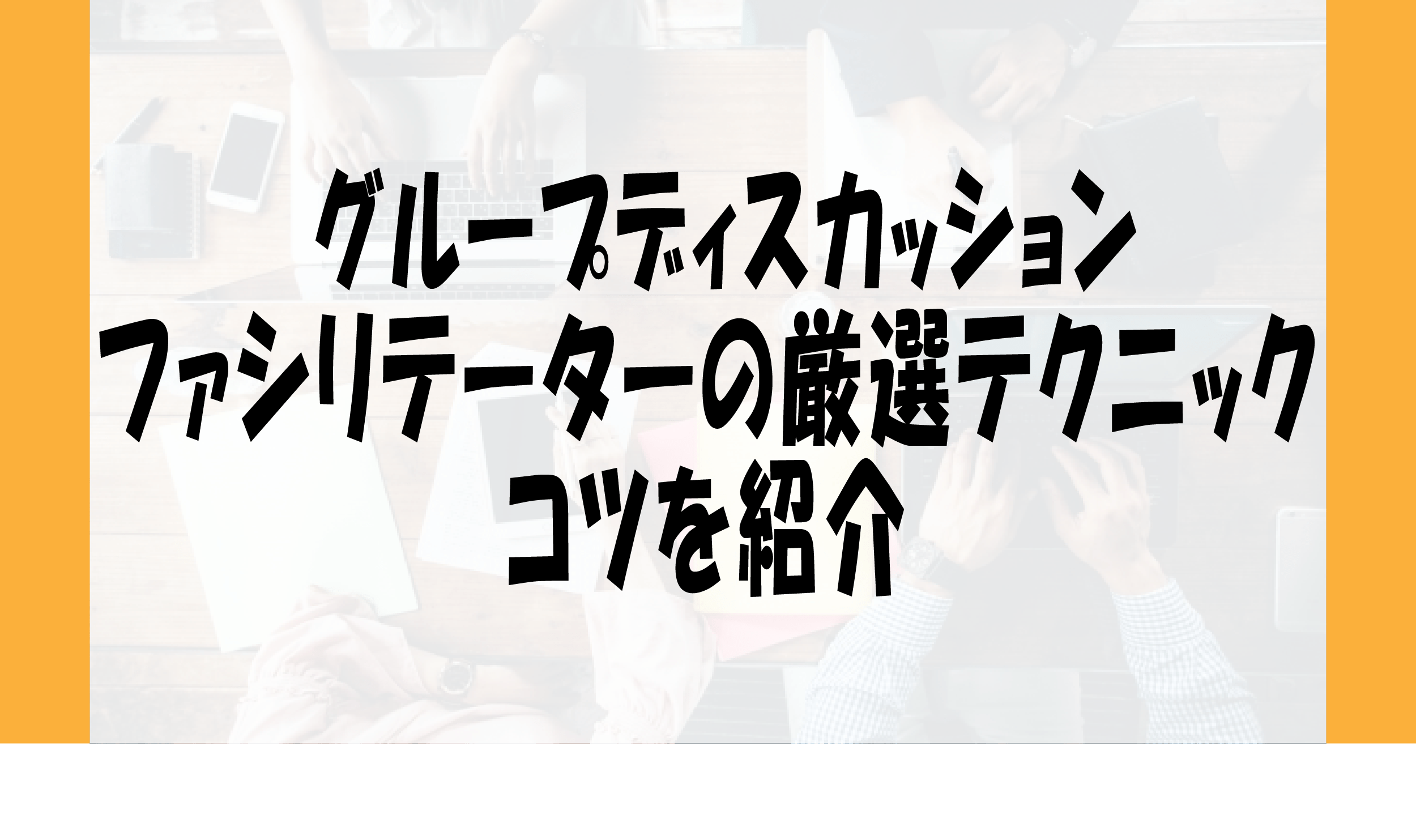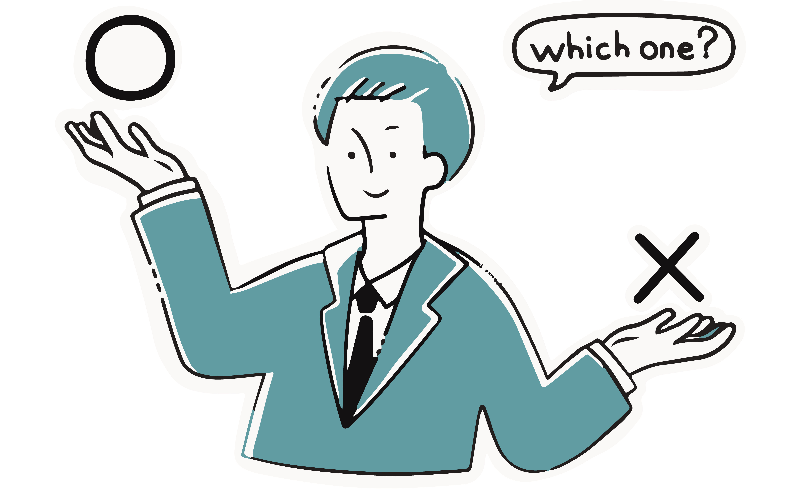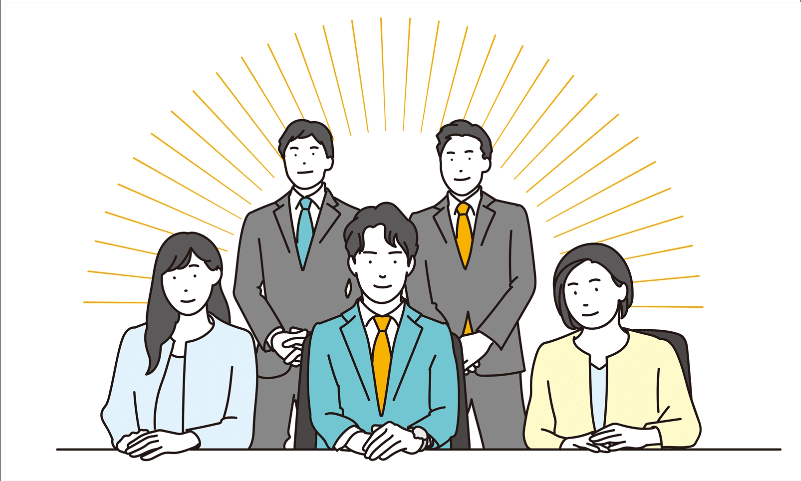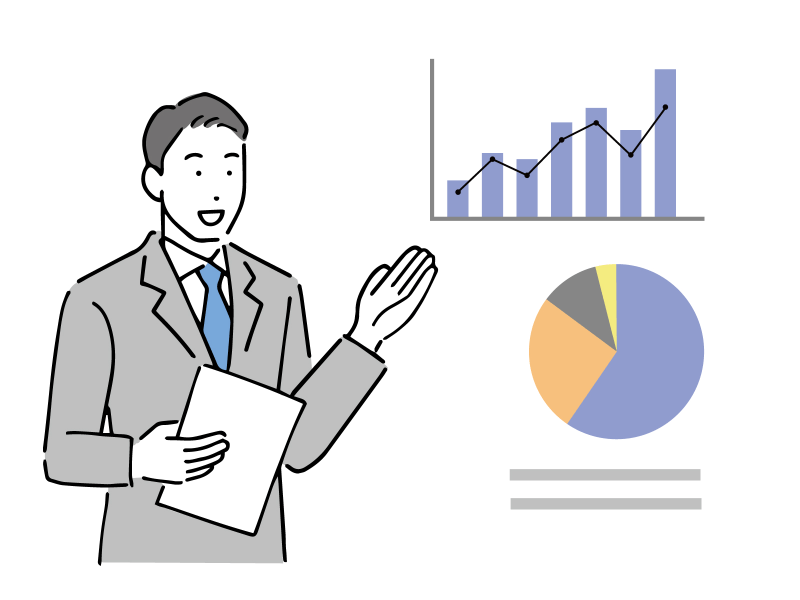グループディスカッションでファシリテーターをやりたい人は多いです。
しかし実際に私が見てきた中でファシリテーターをうまくやっている人はほとんどいません。
というぐらいファシリテーターという役割は難しい役割です。
なので今回グループディスカッションでファシリテーターの議論をどう進めるのかということについて紹介していこうと思います。
ファシリテータとはどんな役割り?
グループディスカッションにおけるファシリテーターの役割は大きく3つあります。
・グルディスの方向を定める
・メンバーの思考をゴールへ方向付ける
・メンバーの協力が協同を促す
それでは各々の具体的な役割を説明します。
GDの方向を定める
グループディスカッションの問題が出されたらまずは、問題を読んで理解しどのように進めるべきかを判断しないといけません。
グルディスの方向性はどのような手順で進めるかの提示と同意を得ることです。グルディスの進め方はグルディスの経験があれば、まずは前提を置いて、目標を定めて、どのような進め方をするかを考えないといけないことは理解しています。
しかし、初めての学生はこの手順を知らない場合もあります。
まずは最初に進め方を提示することが重要なファシリテーターの役割です。
どのような議論を経て解答を導き出すかを提示してコンセンサスをとることが最初の重要な役割です。
メンバーの思考をゴールへ方向づけする
人間は論理と感情で相手の意見を受け入れる傾向があります。
論理的に正しい進め方であっても相手の気持ちや感情を理解して進めないと同じ意識と気持ちで目標に向かうことはできません。
参加者の気持ちを一つにまとめることが重要な役割です。
メンバーの協力や協同を促す
グループディスカッションはケース面接とは異なり、グループでコンセンサスを得ることが目標です。そのためには参加者全員が前向きに参加する体制を作ることが最も重要です。
確からしい答えを出すのが目的ではなく、全員で協力して確からしい答えを出すことです。
そのためにファシリテーターは全員が参加し、協力して和気藹々と議論が出来る雰囲気を作り出すことが重要です。
グルディスの他の役割のコツを知りたい人はこちら
ファシリテーターの進め方のポイント
グルディスのおけるファシリテーターの基本3事項を理解した上で個別にすべき内容を解説していきます。
基本的にはグルディスが始まってからのタイムスケジュールに従ってポイントを説明していきます。
時間配分
問題が提示されたらまずは診断を実施します。
そしてこのグループディスカッションをどのように進めるかの時間的配分を決めます。
・診断
前提確認、目標確認
・検討プロセスの設計
議論の順番
・検討
・まとめ
です。このことを何分で実施しようかと提案します。
よく見かけるのは前提〇分、アイデアだし〇分、まとめ〇分という進め方でこれは何も規定していません。
重要なことは議論の順番を決めて時間配分することです。例えば理想的なダイエット方法を検討してください。という問題であれば、最初に理想的なダイエットとは何かに関する議論に〇分、ダイエットが上手くいかない原因に関して〇分、そして最後に上手くいかない原因を排除した理想のダイエットプランを〇分議論する。
このように議論の順番と議論時間を提示することが重要です。
時間配分は自分で時間を意識しながら実施する方法もありますが、タイムキーパーを指名して設定時間の途中で注意喚起をしてもらうように最初に打ち合わせて進めることも重要です。
全体の雰囲気を良くする
グループ全体の雰囲気を良くするためにはいくつかの方法があります。
この方法を活用することでスムーズに明るい場になります。いくつかのスキルを紹介します。
意見を出してくれたことへの感謝
グループディスカッションに限らず、相手とコミュニケーションをとる場合、親近感を感じることで相手との心理的距離が縮まることが報告されています。
その中でも、意見を出してくれたくれたことに感謝をするというのが重要です。意見を言うとき自信満々に発言する人がいる一方で、やっとの思いで意見を絞り出す人もいます。
そういうタイプの人は否定されたり、受け入れられないと次に意見を言う機会を失います。そういうタイプに向けては意見を言ってくれたことに対してまずは感謝することが重要です。
あなたの対応によって、次回も意見を出そうとする勇気が出るのです。
意見への共感
意見を言った時に周りに受け入れられるかどうかは発言者にとっては重要です。
否定されれば、反発もしくは傷心のどちらかです。まずは褒める。いい意見だね。
と一旦受け入れ、もし気になる点があれば、部分的な修正を加えるのがいいでしょう。YES-BUT法という有名な方法です。一旦は受け入れる。共感を示すことが重要です。
話したけど引っ込み思案な人を指名
参加者の全員の様子をいつも注意深く観察することが重要です。
メンバーの中には引っ込み思案だけど素晴らしい意見を持ってる人もいます。発言のきっかけを作ることは重要なファシリテーターの役割です。
オンラインの場合は発言をしたい人は手を上げることが一般的ですが、対面は相手の表情や動作で話したいそぶりを見つけ、発言の機会を促すことも重要です。
状態によって適切に行動する
グループディスカッションはその時のメンバー構成によって大きな影響を受けます。
色々な場面に応じて適切なファシリテーターの役割が求められます。
おとなしい場
皆が積極的な場合は始まってすぐに意見がたくさん出るケースがありますが、メンバー構成によってはおとなしい場となります。
その際は、ファシリテーターは通常と異なる役割を実施する必要があります。
・最初に意見する役
グループディスカッションは最初に誰かが発言をして口火が切られます。
しかし、おとなしいメンバーの場合は最初の口火が切られません。進め方を提示して意見を待っていても意見が出ない場合は、ファシリテーターのあなたが口火を切る必要があります。
最初に意見を言って他の人が意見が言いやすいようにする潤滑材になることです。
・ポイント:完璧な意見を言わない
その際に注意する点は、完璧な意見を言わないことです。
最初に意見の口火を切った人が素晴らしい意見を発言したら次の意見を言う人はハードルが上がりいいずらくなります。
そのためには、完成度の高い意見をわざとしないのです。このことで次の意見の呼び水になります。
完璧な意見を発言して、他の人の意見を促すよりも、不完全な意見、突っ込みやすい意見を先頭バッターとしてあえて言うことでグループの活性化を計るのです。
活発な場・発散型の議論
おとなしい場に対して議論が活発でいろいろ意見が出すぎて発散しすぎるグループもあります。
この場合は、議論の方向をうまく示さないととんでもない方向に行ってしまい、盛り上がったけど意見はまとまらなかったということも多々おきます。
そういうグループの際はまとめ役が重要です。
まとめ役
こういう場でのまとめ役は、活発な場とメリットを生かして方向を提示して、きちんと意見が集約できるようにすることが重要です。
そのために最初に決めた議論の順番に従い、絶えずいま議論しているテーマから脱線しないことを注視しましょう。
ズレたら戻す。この繰り返しです。発散しすぎたら今までの意見をまとめる。
そして足りない要素を提示することです。このことをすることで活発な議論のまま話を集約することができます。
全体の共通認識の醸成
ファシリテーターの重要な役割に共通認識を醸成するという要素があります。
色々な意見が出た時に賛成の意見、反対意見なのかというポジションの整理が必要です。また色々な意見をまとめることで意見の共通化も必要です。
そして重要なのは1 + 1を2以上にまとめ上げることです。色々な意見の相乗効果をアップさせることです。
ここではそのための手法を説明します。
抽象的な言葉は具体的にする
発言の中には誰もがすぐに理解できる意見と何度か確認しないとわからない意見もあります。
特に抽象的に発言されるとその意見の趣旨が分かりにくいことが起きます。
エントリーシートでも起きていますが、「バイト先の売り上げアップのために効率的に率先して仕事をしました」
と発言しても何を効率的に進めたのか、率先とは具体的に何を誰より先に実施したのかという情報がありません。
このように、人の発言には抽象的な概念だけを発言する人は意外に多いのです。
こういう意見に対して、具体的な部分を話させることが重要です。
そのことによって発言の真意がわかります。抽象的な意見を具体的に話してもらう事を促すのも重要な役割です。
意見の理由を確認
そして、発言の中には意見を言っても理由を添えない発言もあります。
これだと発言者の真意がわかりません。例えば、子供をプロ選手にするなら野球とサッカーとどちらが良いですかという問題の場合、サッカーがいいと思う。という発言は理由がないのでどのように扱うべきかわかりません。
その際は、どうしてそう思うのかという理由を質問することが重要な役割です。
もちろん、発言をする際は、結論に理由を加えて意見をするのは基本です。このことでメンバー全員が発言の真意を理解してスムーズに進むことが可能となります。
反対意見を上手に捌く
現在のグループディスカッションにおいて重要な役割は、反対意見の対処の仕方です。
現在の学生は反対意見を全部聞き入れる傾向が強く、全部を受け入れるとそこには明確な主張が無くなります。そのためには反対意見にうまく対処することはとても重要な役割です。
場面に合わない意見や反対意見を上手に捌く
反対意見の処理においては亀裂を恐れてすべて受け入れるのではなく、その意見が議論のテーマとは異なる場合や、反対意見の場合はには、その理由を明確化していくことが重要です。
その際は、「全体の雰囲気を良くする」で説明したスキルを活用し処理しよう。
深い議論に指導
グループディスカッションでよく見かけるのは、それらしくまとまっているが深い議論ではなく、表面的にいくつかの意見をまとめただけというのがよく見受けられる。
単純に複数の意見をまとめただけです。議論は意見をビルドアップ型でどんどん良くすることが重要です。
そのためには意見を戦わせて切磋琢磨する。もしくは、1人の意見を基に更に付け加えてより良いものにする事です。
議論が深くなるには、意見に対して、5W1Hの質問をし吟味することが重要です。
例えば先ほどの「子供ならせるなら野球選手かサッカー選手のどちらが良いか」を問う問題の際に、評価軸を年収が高いほうが良い。という評価軸を誰かが言います。
その時に自問するのです。いつまでの年収が高いと疑問を感じると生涯年収のほうが良いのではという意見が出てきます。
また何歳の時と疑問を感じると年収が最も高いのはいつ頃と考え、ピーク年収の年齢がイメージされます。
そのように考えることでさらに深く議論を進めていけます。
このようにファシリテーターはグループ全体の議論を深くする必要もあります。
面接はマナーを気にするのに、グループディスカッションではマナーを全く意識している人がいません。
そこでグループディスカッションでのマナーを紹介しているのであわせてご覧ください。
たった1日であなたのグルディス対策を完結させます

グループディスカッションに合格するには絶対に実践経験が必要です。
「出会いの場」に参加すると、以下のメリットがあります。
・1日6〜10回の実践による圧倒的練習量
・実際の人事の採点であなたの得意不得意と順位が分かる
・一度に最大10社と出会え、直接企業の本選考に進める
グルディス対策をしたい&1日で就活を大幅に進めたいという方はぜひご参加ください!
ファシリテーターは圧倒的に難易度が高い

優秀なファシリテーターの要件を挙げてきましたが、難易度が高いことは理解できましたね。
このように一人で優秀なファシリテーターをできる学生はほぼいません。
出来た気になっていますが、たいていは不完全です。一番難しいところはやることが多いという点です。
やることがめちゃくちゃ多い
良いファシリテーターは、グループディスカッションが始まる前にメンバーが決まったときに、自己紹介やアイスブレイク時にメンバー1人1人の性格やタイプ、そして能力をある程度観察して把握する必要があります。
そして始まれば、問題をすぐに把握して進め方、議論の順番を決めて、真っ先に発言して、議論方向をきめます。
そして議論の間もずっと、時間を気にして、メンバー全員の様子を観察して、意見の流れを把握します。
時には自分が発言して議論の方向を作る必要もあります。このようにやることがとても多いのです。
だがうまくやれれば超高評価
この重要な役割を完璧に勤め上げられれば、高い評価になります。
ここで書かれたとおりにできればこの後の面接などで落ちることもほぼないです。
この能力は仕事を進める上でも重要な能力です。
完璧なファシリテーターができる人材はどこの企業でも最も欲しい人材です。
ファシリテーターのコツ
それではこのファシリテーターを完璧に努めるために必要なスキルをここでお伝えします。
常に周りを観察
ファシリテーターは常に参加メンバー全員の様子を観察して評価しておくことが重要です。
メンバー個々の、コミュニケーションスキル、グループディスカッションのスキル、グループディスカッションの経験値、性格を把握する必要があります。
それでは観察ポイントとなぜ必要かを説明します。
メンバーのコミュニケーションスキルを見る
コミュニケーションのスキルの中で、発現する力を見ておく必要があります。
発現する力は発現の頻度、量と質ですね。この3要素が兼ねそろっている学生ばかりではなく、秀でている要素と劣っている要素、平均的な要素と見抜く必要があります。
平均的な人が多いほど、スムーズに進行できますが、面白い、深い議論にはなりません。秀でている要素をうまく引っ張り出します。劣っている要素をカバーしてあげることが求められています。
メンバーのグルディスの経験値
グループディスカッションの経験知の理解は重要です。未経験者は基本的な進め方を理解していません。
まずは未経験者に基本的な進め方を理解させる必要があります。
次は経験の量と質ですが、特に重要なのは質の把握です。
沢山経験すれば慣れますが、それはおしゃべりがうまくなっているにすぎません。
質とはどういう問題の経験をしているかです。課題解決型をうまく進めるにはロジカルシンキング型のグループディスカッションが不可欠です。
グループ全体のレベルを把握してレベルにあった議論を進めることが重要です。経験の浅い人が多い場合は論理性を弱める必要もあります。
メンバーの性格
メンバーの性格の中でも、内気なのか社交的なのかは重要です。
内気な人には発言の機会を提供し、外交的な人にはしゃべられすぎないで独り相撲を防止する必要があります。
特に注意すべきは批判的な人、攻撃性が高い人をきちんと観察してうまく対応する必要があります。
この手のタイプは扱いかたを失敗するとクラッシャーになってしまいます。
そして非論理的な人、思い付きで話す人にも注意が必要です。
この2つに共通する点は、意見と理由を聞いても整合性が無いことです。整合性が無い人の意見は取り扱いが難しいです。
質問などでその隙間を埋めることが求められます。論理性を持たせる架け橋をかけてあげることです。
それ以外でチェックするところ
それ以外でチェックすることは、メンバーの表情、姿勢、声の大きさや話す速度です。
・表情テンション姿勢声の大きさ話す速度
特に表情から、このグループディスカッションにどのくらい馴染んで参加出来ているかがわかります。うまく参加できていない人や話したいけど話せてない人を表情から推察しましょう。
そして姿勢も同様にチェックポイントです。それに加えて、メンバーの姿勢を変えることで全体の盛り上がりも変わりますから、うまく盛り上がっていない場合は向きなどを変える必要があります。
声の大きさと話す速度は緊張度合いを表しています。
緊張している人をリラックスさせます。また攻撃的な的なコミュニケーションの人を和らげる必要もあります。
・全体の雰囲気
全体の雰囲気は重要です。
みんなが楽しく参加できているチームは全員合格します。全体の雰囲気を常に観察して明るい、和気あいあいとしたチームを作りましょう。
最初に進む手順を説明する
グループディスカッションが始まったらまずは手順を説明しましょう。
最初に与えられた時間を何にどのくらい使っていくかを提示します。
メンバーを結論に導いていく必要がある
グループディスカッションはおしゃべりの場ではありません。
全員で合意して結論を出すということが使命です。そのゴールを全員で共有しましょう。
最初に何を議論して次に何を議論してまとめて結論を出すのように
ファシリテーターの中でも最も重要なことがこの議論の順番を決めることです。
良くグループディスカッションで、アイデアだし〇分、まとめ〇分というのは見ますが、重要なのは何の議論をするかの提示です。
この議論の順番の提示こそが最も重要な役割です。
手順を序盤に説明しておく
最初に、この問題を解く上でこういう議論をこの順番でする。
そして議論をする上で前提を最初に〇分で決めよう。今回の議論は体験談をもとに話そう。とか決めて全体の進め方を提示することです。
最初に提示することでメンバーは迷うことなく進むことが出来ます。
基本的には中立を意識する
ファシリテーターの基本は中立です。
誰かに物事を強く肩入れすると不公平となります。あくまでも最も良い解答が出る為に進行する訳です。
意見が出ないときに発言する際も呼び水の役割であり、その意見が大勢を占めるような意見であってはいけません。
最も重要な点は、周りが意見を出しやすくなるという点に力を注ぎましょう。
時間がない結論を出さなければならない、話が逸れそうな場合以外は中立
しかし、議論がうまく進まないで時間内に解決できないときは中立性を破っても答えに導かないといけません。
特に多いのは議論が出ないというグループの場合です。この際は、自分の意見が呼び水を超えて方向を指し示さねばなりません。
しかし、伝家の宝刀は何度も使ってはいけません。また、話が大きくそれる場合は戻さないといけません。
特に意見が割れてる場合はどちらかに肩入れしてでも意見の統一が必要となります。そういう際は中立性を棚に上げ、結論に向かわせましょう。
合意形成をする
ファシリテーターは合意形成する事が重要です。
合意形成とは議論によって答えを見つけることです。
安易な妥協、多数決をしてはいけません。議論によって合意形成をすることを心得ておきましょう。
ここまでの議論は大丈夫で結論はこれだという合意をもらう
その為にも議論の途中でここまでは合意できていますよね。
という確認を実施しましょう。途中の合意形成をしないとメンバーもどこまでも決まった事か合意されたかわからなくなります。
途中の合意の確認も重要な仕事です。
グループディスカッションをスムーズに進めるには議論の流れを知っておかないといけません。テーマの型によって議論の流れが異なるので、こちらもあわせてご覧ください!
ファシリテーター注意点

それでは最後にファシリテーターであるあなたが注意すべきことをおさらいします。
・発言しすぎない
・一番に名乗りをあげない
・「でしゃばり」だと思われる。
・人の発言を真っ向から批判や否定をしない
この4点をいつも意識しましょう。この中でも多くのファシリテーターが陥りやすいのは、発言しすぎるて出しゃばりだと思われるということでしょう。
ここに挙げている点には十分に注意をしましょう。
ファシリテーションをやると落ちるってほんと?
このような話がSNSで流れていますが、信憑性は低いです。
優秀なファシリテーターはどこでも取りたい人材です。
こういううわさが流れるのはファシリテーターが役割を認識しないで実施するか、それとも理解するがうまくできないかで実際のグループディスカッションをうまく仕切れなく、評価が低かったことが原因だと思われます。
まとめ
今日はファシリテーターについて述べました。
グループディスカッションにおけるファシリテーターは重要な役割です。
多くの学生が本当のファシリテーターを理解していません。本当の役割を認識して、完璧にこなせばグルディス無双になれます。
ぜひこの文書を参考に素敵なファシリテーターになって、グルディス選考を突破してください。
この記事と併せて読みたいグループディスカッションの厳選記事
・グループディスカッションにいるクラッシャーの対策方法を知りたい人におすすめ記事
→グループディスカッションにいる8種類のクラッシャーの対策方法を紹介
・グループディスカッションの練習方法ってなにがあるの?という方におすすめの記事
・グループディスカッションの絶対に受かりたい人におすすめの記事