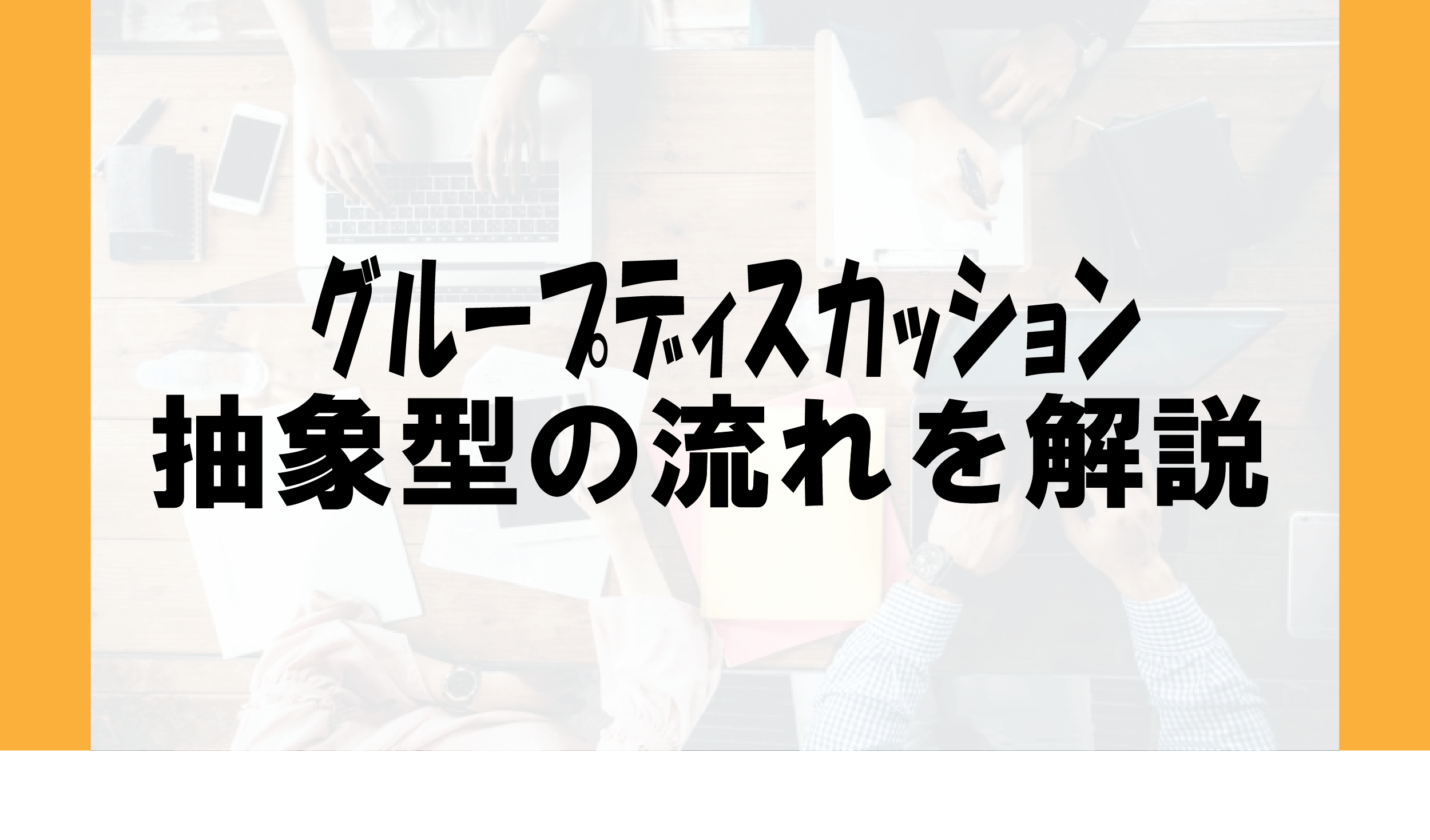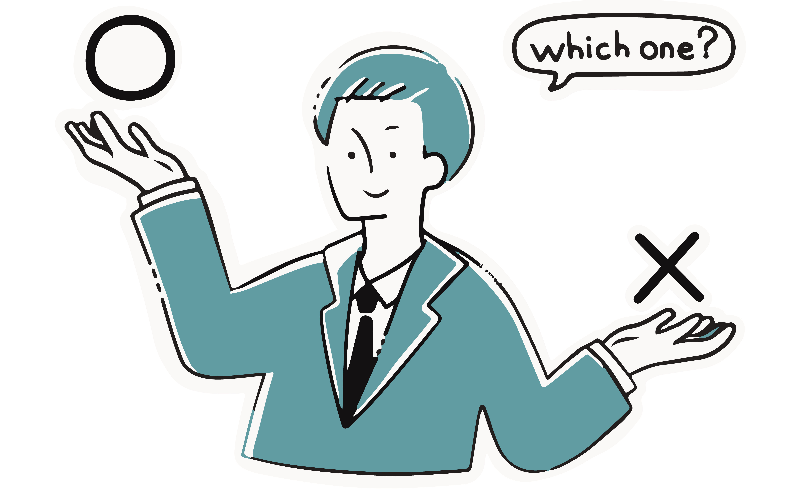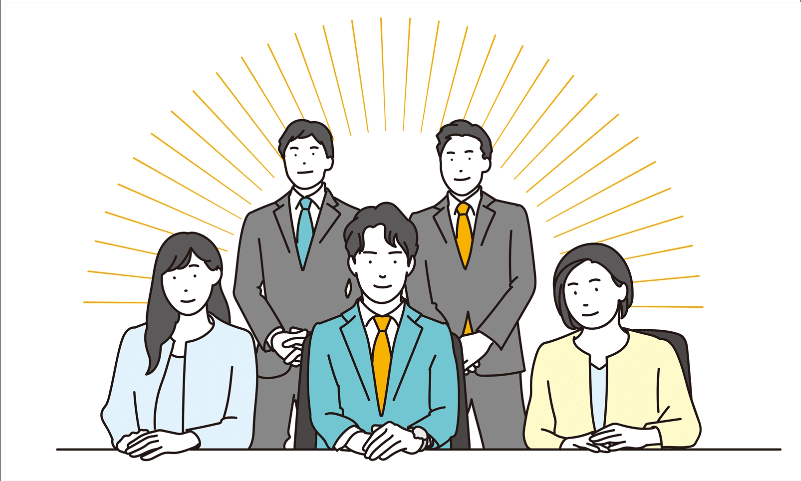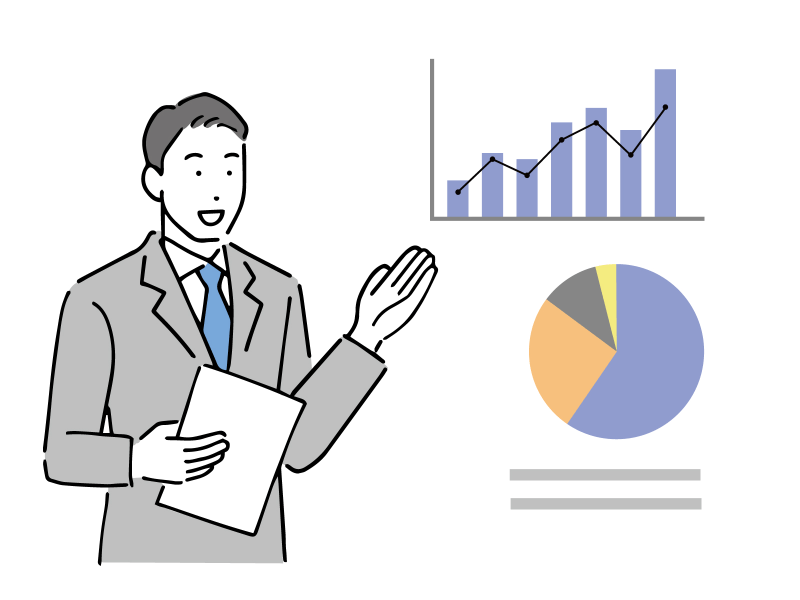勘のいい人はグループディスカッションをやっていると大体流れが一緒だなと感じると思います。
実はその通りにグループディスカッションの出されるテーマには大体3つの型で出来ていて、その型は大体が流れが決まっています。
その型の中でも今回は抽象型の解き方の流れを紹介していこうと思います。
グループディスカッションの抽象型の問題とは?
「抽象型」とは、抽象的なものや不明瞭なものを具体的な言葉で定義するタイプの問題です。
たとえば、次のような問題です。
・「幸せなキャリア」とは何か検討してください。
・中学校に新しい科目をつくるなら、何にすべきか検討してください。
・日本の魅力を世界の人に伝えるにはどうするべきか、検討してください。
抽象型の議論の流れとは?
では早速抽象型の議論の流れを紹介していこうと思います。
1、前提と目標の定義
「前提」と「目標」を決め、グループ全員で目線を合わせます。
「前提」とは議論を成立させるために必要な要素、
「目標」とはGoal、つまり目指すべき結論のことです。
抽象型は最初に定義をしっかり固めていないと、後から議論がまともに出来ず、また前提に戻るという感じで2度手間になりやすいです。
なのでしっかりと前提と目標を定義するようにしましょう。
2、考え方の判断軸の決定
「抽象型」の問題は、「抽象的なもの、不明瞭なもの」を具体的な言葉で定義する問題です。
どのようなものを目指すか、方向を決めなければ、議論はあらぬ方向に進んでしまうでしょう。
そこで、考え方の判断軸を決めることがポイントとなります。判断軸となる要素は1つとは限りません。
3、アイデアの発案
2、決めた判断軸にもとづいてアイデアを出し、結論へとまとめていきます。
抽象型以外のテーマの流れも理解しておきましょう。
抽象型の流れの解答例紹介
では先ほどの抽象型の議論の流れに則って、テーマの解答例を紹介していきます。
幸せなキャリア」とは何か検討してください。
1、前提と目標の定義
①前提の定義
議論を行なうために必要な要素として、今回は「誰にとって」について定義します。
「幸せ」の考え方やキャリアについての捉え方は人それぞれ違います。
グループディスカッションには必ず制限時間があり、世の中のあらゆる人を網羅する結論を出すには時間が足りません。
年齢や職業、性別などの人物像を設定し、その人物にとっての幸せなキャリアを検討していきます。
今回は「大学生、男性」と定義することにします。
②目標
今回の議論のゴールは、「幸せなキャリア」という抽象的なものを具体的に定義すること。
「キャリア」という言葉は、特定の時期に限って考えるか、社会に出て働く期間全体を考えるかによって、意味合いが違います。
本格的な議論を始める前に、全員でこの認識を揃えておくのが良いでしょう。
今回は「キャリア=社会に出て働く期間全体」とします。
「大学生、男性」にとっての「幸せなキャリア(社会に出て働く期間全体)」を定義する、という問題になりました。
2、考え方の判断軸の決定
3、アイデアの発案
この問題の場合、判断軸は「幸せ」をどう捉えるかによって異なります。
「幸せ」とは、価値観によって大きく異なります。また、あまりにも抽象的すぎる概念でもあり、考え始めると終わりがありません。
ですので、無理に一般論を出す必要はありません。各々の考えを積極的に出していくのが良いでしょう。
但し、ただ各々の考え/意見を主張し合うだけでは、論理的な議論とは言えません。
集まった意見を体系的にまとめて結論を導く必要があります。
そこで、「KJ法」という手法を使ってみます。
【KJ法】
①発散:アイデアを出す
②分類:①のアイデアのうち、似たものをグループにまとめる
③要約:②でまとめたものを文章化
①発散
前提=「大学生、男性」にとって何が幸せか意見を出し合います。
これまでの人生でどんな時に幸せだと感じたか、それぞれの実体験を元にアイデアを出し合うと、抽象的な議論を避けられます。
たとえば、
A)猛勉強して志望大学に合格した
B)高校時代の部活動で、猛練習してレギュラーになった
C)面倒見のよさを認められ、サークルの副代表に就任した
D)バイト先で表彰された
等々、具体的なエピソードを出し合います。
②分類
①のアイデアを似たもの同士のグループに分類していきます。
今回の場合は、
目標を達成したグループ:ABD
まわりの人に認められたグループ:BCD
に分類することが可能です。
③要約
②をまとめると、「幸せなキャリアとは、目標を達成し、まわりに認められること」という結論になります。
中学校に新しい科目をつくるなら、何にすべきか検討してください。

1、前提と目標の定義
①前提の定義
中学校の教科は、中学生がその時期に身に着けるべき素養を育成するものです。
そしてその素養とは、将来役立つもの、将来必要になるものですので、
今回は前提として、「(対象となる中学生にとって)いつ必要になる素養なのか」を目線合わせします。
今回は、「社会で働くようになる頃=20代で求められる素養」としてみます。
②目標
今回の議論のゴールは、「中学校の新しい科目」という、今はないものを作る、企画することです。
中学生という時期にどのような学習が必要になるか(実用性?知識?精神的な成長?)目線合わせします。
今回は「実用的な能力を伸ばす学習」とします。
中学校で、「20代で求められる素養」で「実用的な能力」を身に着けられるような新しい科目をつくるなら、何にすべきか検討してください、という問題になりました。
2、考え方の判断軸の決定
「中学生が将来(=前提として定義した時期)求められる素養」で「実用的なもの」を具体的に検討していきます。
社会で働くようになる頃=20代には、どのような能力が必要になるでしょうか?
抜け漏れ・ダブリなく挙げていきます。
たとえば、
A)コミュニケーション能力:他者と円滑に関係構築する能力
B)発信力:自分から発信する能力
C)リーダーシップ:自分から動く能力
このままだと抽象的なので、もう少し具体的に分類します。
A)コミュニケーション能力→相手のニーズを聞き取る、ニーズに沿った提案をする
B)発信力→自分から発言する、自分の意見を正確に伝える
C)リーダーシップ→集団をまとめる、誰より早く動き出す
3、アイデアの発案
ここで決定した判断軸を満たすような科目は何か検討します(例:ディベート、フィールドワーク・・・など)。
既存科目で補えない素養があればそれを補うような科目を検討し、既存科目ですべて補っているとすれば強化するような科目を検討します。
日本の魅力を世界の人に伝えるにはどうするべきか、検討してください。
1、前提と目標の定義
①前提の定義
議論を行なうために必要な要素として、「世界の人とは誰か」「何のために日本の魅力を伝えるか(目的)」について定義します。
伝える対象を定義します。年齢、性別、地域など、ターゲットを設定します。
たとえば、「スペインに住む20代の若者」と定義してみます。
次に、彼らに日本の魅力を伝える目的は何かを目線合わせします。
この問題は、最初に「日本の魅力を伝えるやり方」を決めてから外堀を埋めるような、結論ありきの議論になりやすい問題です。
アイデアから先行するのでなく、何を以てふさわしいとするか=判断軸を決めてから、ふさわしいアイデアを挙げる必要があります。
この問題の場合、「日本の魅力の中でどんなものを伝えるか(アイデア)」にフォーカスしやすいのですが、その一歩手前、「何のために日本の魅力を伝えるか(目的)」という部分が重要です。これが何かによって結論は大きく異なります。
目的とは、たとえば「日本の伝統を理解してもらうため」「日本を好きになってもらうため」などが挙げられます。
目的が「日本の伝統を理解してもらうため」であれば、例えば日本を代表するアニメやマンガといった、既に広く知られているものは外れていきます。
アイデアを出す前に、「何のために日本の魅力を伝えるか(目的)」を設定して目線合わせしましょう。
先ほど、伝える対象は「スペインに住む20代の若者」と定義しました。
彼らに「日本をより好きになってもらうため」に日本の魅力を伝えることにします。
つまり、「スペインに住む20代の若者に日本をより好きになってもらうには、日本の魅力の何をどのように伝えるべきか」という問題になりました。
②目標
今回の議論のゴールは、日本の魅力を世界の人に伝えるにはどうするべきか=最適なやり方を具体的に検討することです。
2、考え方の判断軸の決定
「スペインに住む20代の若者」が「日本をより好きになるため」の要素を検討します。
・日本人の友達ができる
・日本人と共通の趣味で楽しめる
・日本に興味を持つ
等々が挙げられます。
3、アイデアの発案
・同じマンガが好きな日本人とマッチングできるサービスを展開する
・同じゲームをプレイしながらのオンライン飲み会を設定できるサービスやツールを作る
・キモノの縫い方や着付けの無料講座をオンラインで配信する
等々です。判断軸を最も満たすものを絞り込んだり、出たアイデアを組み合わせるなどして、結論にまとめていきます。
たった1日であなたのグルディス対策を完結させます

グループディスカッションに合格するには絶対に実践経験が必要です。
「出会いの場」に参加すると、以下のメリットがあります。
・1日15分×4回の実践による圧倒的練習量
・実際の人事の採点であなたの得意不得意と順位が分かる
・一度に最大14社と出会え、直接企業の本選考に進める
グルディス対策をしたい&1日で就活を大幅に進めたいという方はぜひご参加ください!
まとめ
抽象型の問題は、具体的なアイデア出しが先行しやすいタイプの問題です。
論理的な議論を構築するには、まず判断軸を設定することがポイントです。
また、アイデア出しのやり方には、今回紹介した「KJ法」のほか、「オズボーンのチェックリスト」などもあります。
いくつか発想方法を身に着けておくと、実際のディスカッションでも役立つでしょう。
この記事と併せて読みたいグループディスカッションの厳選記事
・グループディスカッションを初めて受ける人におすすめの記事
→初めての人でもグルディスを通過する具体的な10つのSTEP
・グループディスカッションにいるクラッシャーの対策方法を知りたい人におすすめ記事
→グループディスカッションにいる8種類のクラッシャーの対策方法を紹介
・オンライングルディスの注意点を知りたい人におすすめの記事