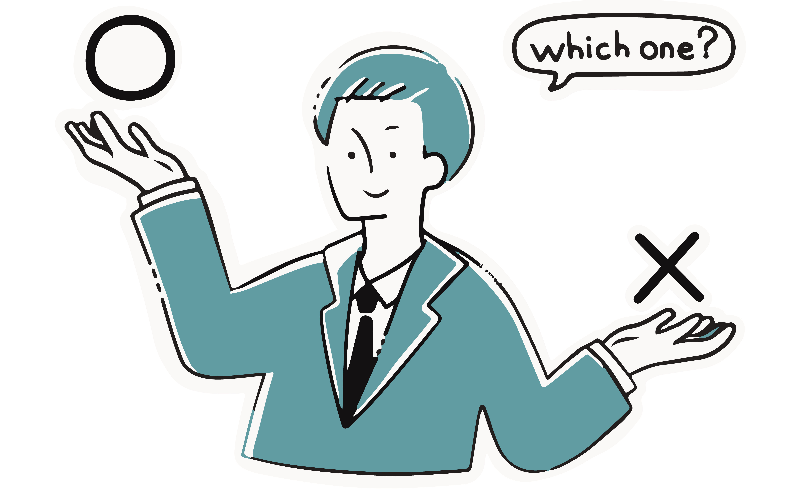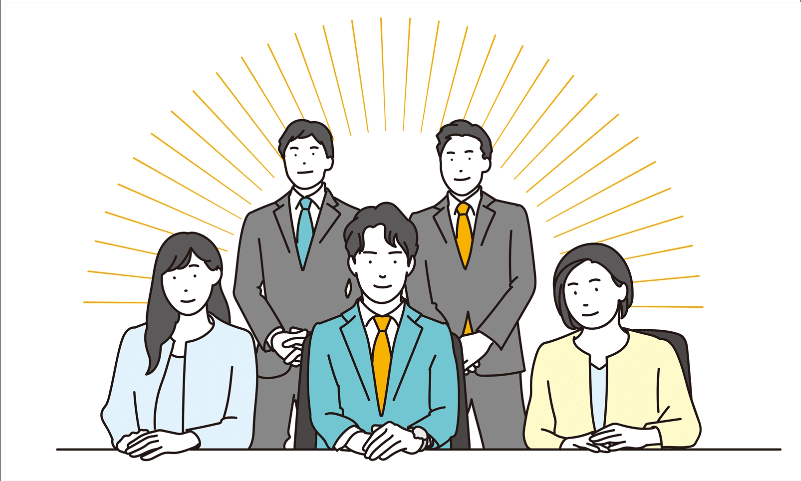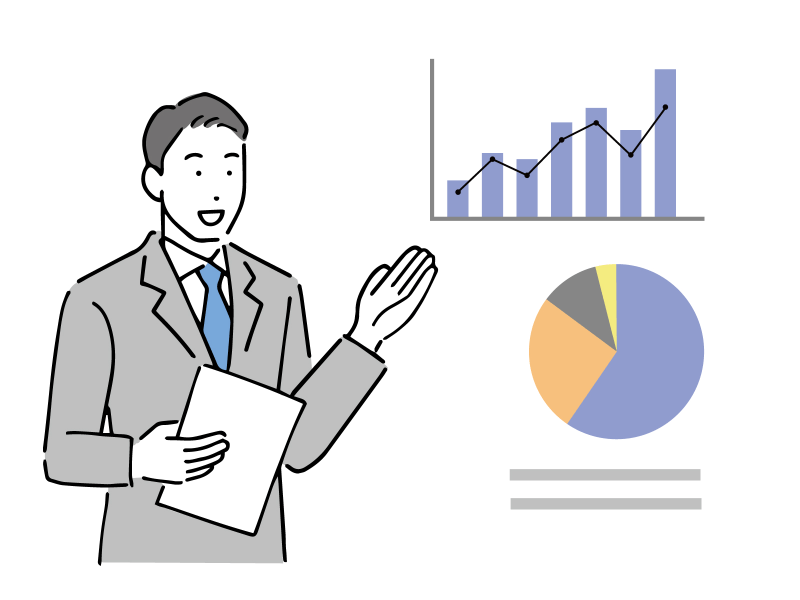就活生・佐藤さん
コンサル志望の大学3年生。グループディスカッション(GD)は割と得意。実力をさらに磨くため、プロ講師のもとで特訓中!

就活プロ講師・清水さん
DEiBA Company代表取締役でYoutuber。元リクルート常務。
「DEiBA就活チャンネル」や就活対策セミナーでグループディスカッション(GD)を教えるプロ講師。
「なぜ人はお酒で失敗してまた飲むのか」という問題を考えます。
佐藤さんの解き方
1.前提
・お酒の失敗とは?
①人に迷惑をかける
→例:介護、失言、暴言、暴力
②損害を被る
→例:怪我、体調不良
・どこで飲むと失敗するか
→度数の高いお酒が販売される場所:宅飲み、大衆居酒屋、クラブ、など
・なぜこの議論をするのか
お酒のやめ方を知るため
2.現状分析
失敗しても再度お酒を飲む理由:
心配<お酒の楽しさ
・お酒の心配について
→お酒の心配は日に日に減少する
一度犯した失敗から学び「次は気を付けよう」となりがち。失敗することでお酒との向き合い方が考えられる。
・楽しさについて
→人は快楽のレベルを下げることが難しく、同じ楽しさを求める。
適切な飲酒量はコミュニケーションを活発化させ、他人との距離を縮めることができる。
ここで生じた快楽は忘れられず、コミュニケーションにお酒が必要不可欠になる。
3.打ち手立案
①お酒失敗への心配の増大
②お酒の楽しさを減少
の2点から考え、以下の3点が立案された。
⑴お酒の失敗例を学ぶ
飲酒で人生に悪影響が出てしまった事例を検索。他人ごとではないことを知る。「怪我」や「人間関係の悪化」などが反面教師になりそう。
⑵お酒のデメリットを学ぶ
お酒が身体や生活に悪影響を及ぼしていることを知る。メタボに繋がっていないか?お酒を飲んでいる時間を資格勉強などの有益な時間に回せたのではないか?など考えてみると良さそう。
⑶お酒なしで楽しめる友人を作る
高校時代の友達やスポーツ仲間など、派手な飲み会をせずとも楽しめる人付き合いを増やす。
4.打ち手評価
3つの案の
①お酒失敗への心配の増大
②お酒の楽しさを減少
への効果の大きさを考える。
| ① | ② | |
| ⑴ | 大 | 小 |
| ⑵ | 中 | 小 |
| ⑶ | なし | 大 |
以上の表から最も効果的なのは⑴お酒の失敗例を学ぶである。
プロ講師の解説
抽象型>検討型の詳しい解説はこちら
※「某動画配信サイトの人気配信者であると仮定し、チャンネルを売却してほしいといわれた場合、いくらで売るのがよいか」という問題を使って解説しています。