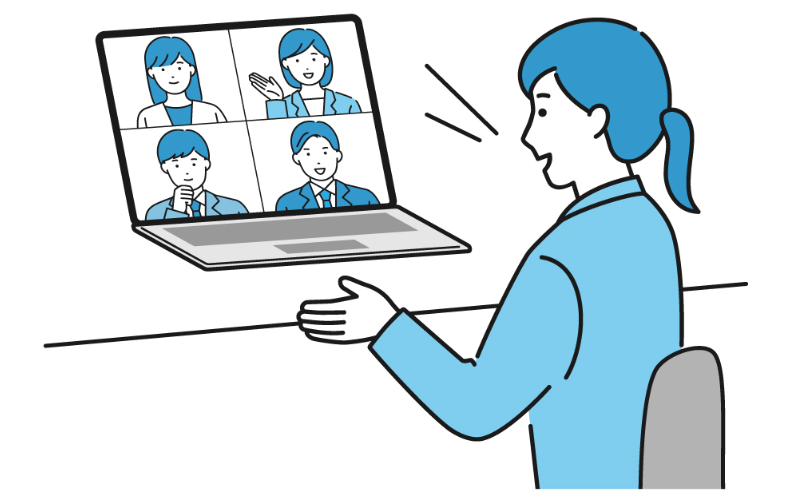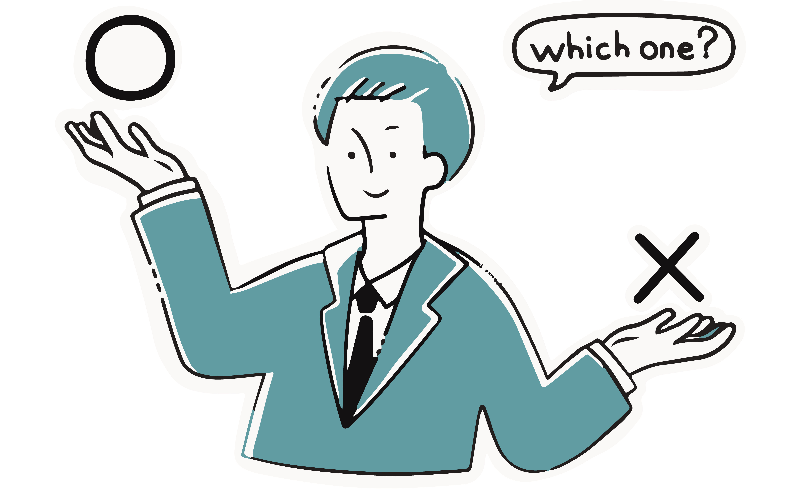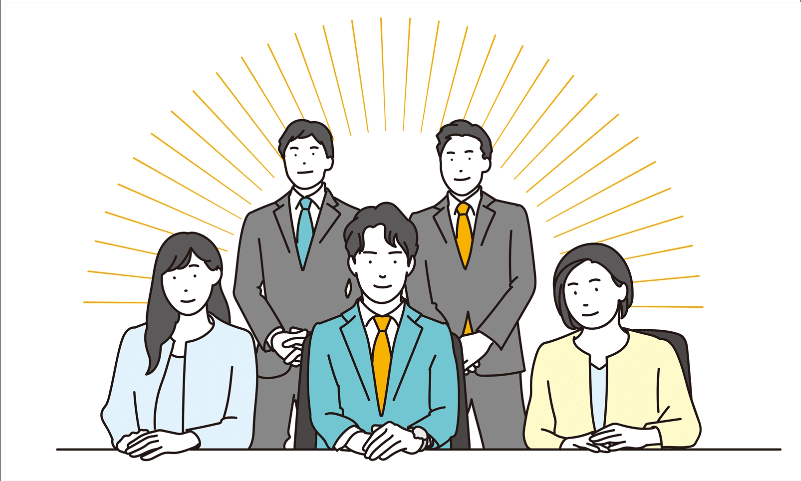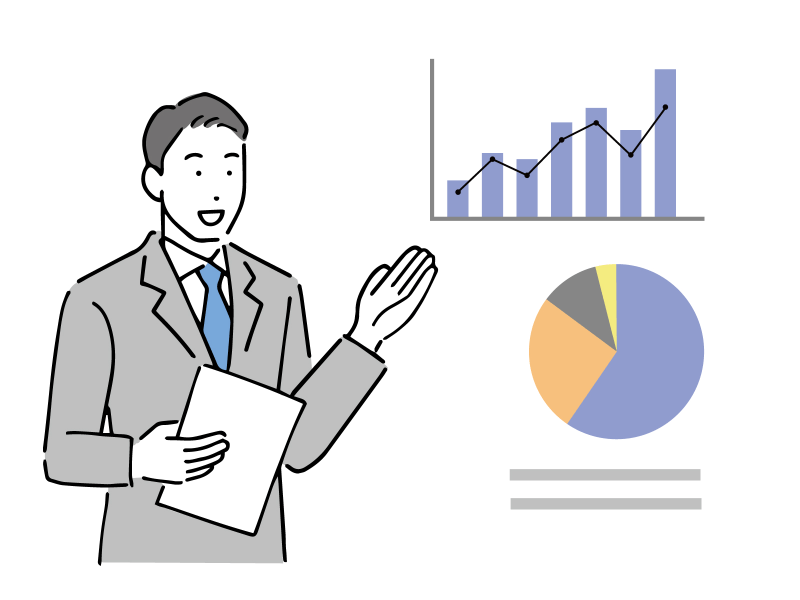グループディスカッション初心者には、グループディスカッションの基本的な流れをあまり知らなかったりします。
流れを理解しておくことで、自分がメンバーを率いることができるのでグルディスを有利に進めることができるようになります。
なので今回はグループディスカッションの流れを紹介していこうと思います。
グループディスカッションの基本的な流れ
グループディスカッション選考は基本的に以下の流れで進行します。
1、自己紹介
グルディスを行なうメンバーは初対面であることがほとんど。この後の議論を円滑に進めるためにも、お互いの距離を縮めることは必須です。
相手に親しみを持ってもらえるよう、自身について伝えましょう。基本的には以下を伝えるようにします。
・氏名
・学校名
・その他(例:意気込み、趣味、特技、研究内容、部活動、サークル等)
・あいさつ
最低限、氏名と学校名は伝えましょう。
まれに企業から、学校名を伏せるように、あるいは特定の項目(ゼミの研究内容やサークル活動など)について述べるように指示がある場合もあります。
その際は指示の通り自己紹介をします。
例「デアイバ大学 経済学部の出会場太郎と申します。大学ではテニスサークルに所属しており、中学時代からテニスを続けているため、元気のよさには自信があります。
グループディスカッションはまだ2回目で緊張していますが、皆さんと一緒に有意義なディスカッションにしたいと思っています。本日はよろしくお願いします。」
自己紹介の目的は「議論を円滑に進めるためにお互いの距離を縮めること」です。
あくまで簡潔かつ端的に述べましょう。
熱が入って時間が長くなってしまうと、「周りが見えていない(協調性がない)」「時間にルーズ」などマイナスの評価になりかねません。
また、他のメンバーの自己紹介にもしっかり集中すること。
頷いたり相槌をうったりするなど、「聞いている」際の態度も重要です。
2、アイスブレイク
アイスブレイクも「議論を円滑に進めるためにお互いの距離を縮める」ために行なわれるもの。
具体的には自己紹介の深掘り、雑談、ミニゲーム等です。
グループディスカッションは制限時間があるため、先に述べた自己紹介をアイスブレイクとする場合もあります。
企業からアイスブレイクとして、グループディスカッションとは異なるお題が出されることもあります。その際はお題について議論することになります。
3、テーマや時間、ルールが伝えられる
お互いの距離が縮まったら、いよいよグループディスカッション開始です。
まず企業から、議論のテーマ、制限時間、ディスカッションの際のルールが伝えられます。
なお確認メールや会場入室時のタイミング等、事前に伝えられる場合もあります。
4、役割決め
ディスカッション選考が開始したら、まずは役割を決めましょう。
グループディスカッション選考は、グループ全員で各々の役割を果たし、より良い議論をして、全員で合意形成した結論を導く必要があります。
役割が割り当てられなかったからと言って、選考に落ちるとは限りません。逆も然りです。
重要なのはグループ全員で各々の役割を果たし、より良い議論を進めること。基本的には自分の得意分野が活かせるものを選びましょう。
もし議論が滞った場合には、一度決まった役割を後から他のメンバーに譲ったり交代したりするのも手です。
主要な役割は以下です。兼務することもあります。
・ファシリテーター:議論の進行役のこと。
他のメンバーの意見を引き出しつつ、結論に向けて議論を導いていきます。人事から最も目立つポジションです。全体の流れを把握する能力や、思わぬ意見が出た際など臨機応変に対応するスキルが求められます。
・書記:議論の内容を記録します。
議論をすばやく理解し、要旨を構造的にまとめる論理的思考力が求められます。抜け漏れなく記録する速記やタイピングのスキルも必要です。
・タイムキーパー:時間を管理する役割です。
単に「〇分経過」「残り〇分」と読み上げるのではなく、議論全体の進捗を把握しながら時間配分を変更する、臨機応変な対応力が必要です。
・発表者:結論とそれに至るまでの議論の要旨について発表する役割です。
ただ書記の記録を読み上げるだけでは不十分。自分なりに要旨をまとめ、抑揚をつけながら話す必要があります。
役割が割り当てられなかった人は、積極的に発言して議論に貢献しましょう。
議論を崩壊させる「クラッシャー」にはならないよう要注意!自分の意見ばかり主張したり、他のメンバーの発言を遮ったり、逆にまったく口を開かず黙っていたり…はNGです。
ただ自分の意見を主張すれば良いというわけではなく、議論があさっての方向に行かないよう、流れを把握しながら発言する必要があります。
5、時間配分
議論の時間配分を設定します。
大枠は以下の流れとなります。
前提確認→プロセスの設計→議論→議論のまとめ
以降、次の問題を例として説明していきます。
例題:新婚旅行先としてふさわしいのは、北海道と沖縄のどちらが良いか、検討してください。
この問題は「選択型」というタイプで、複数の選択肢からふさわしい回答を絞り込む問題です。
6、テーマの前提を決める
議論を成立させるために必要な要素を設定し、全員で目線を合わせます。
例題では、「①新婚旅行するのは誰か」と、「②新婚旅行」そのものについて設定する必要があります。
①カップルの年齢、職業など
例)25歳同士、会社員と専業主婦、本州在住
②旅行の時期、期間、行先など
例)10月、5日間、行先は主要都市の周辺とする(北海道=札幌周辺、沖縄=那覇周辺)
7、プロセスの設計
どのように議論を進めるか、進め方を設計します。
例題は北海道か沖縄かふさわしい方を選ぶのがゴールなので、以下のようなプロセスで進めていくことになるでしょう。
①評価の基準を設定する
②①の基準を用いて、選択肢を比較検討する
③選択肢のうちより基準を満たしたものを選ぶ
ここで各プロセスの時間配分も決定しましょう。
タイムキーパーは、実際の議論の進行を加味しながら、必要に応じて臨機応変に時間配分を修正していきます。
8、議論(アイディア出し&まとめ)
設計したプロセスに沿って具体的に議論を進めていきます。
①評価の基準を設定する
何を以て「新婚旅行にふさわしい」とするか、評価となる軸を設定します。
②①の基準を用いて、選択肢を比較検討する
設定した軸に沿って、北海道と沖縄のメリット・デメリットを挙げ、比較していきます。
③選択肢のうちより基準を満たしたものを選ぶ
今回は「北海道」と「沖縄」から、より多くの基準を満たした方を選びます。
ディスカッションの大前提は、「全員で合意形成しながら結論を導く」ということ。
つまり、グループ全員が納得していなければ、結論として不十分です。
全員が納得するためには、論理的な説明で理解を得てもらうことが不可欠です。
発言の際は以下を意識しましょう。
・結論から話す
・その意見に至った理由を説明する
・具体的な例を挙げる(抽象的だと伝わりにくい)
例)「評価の基準として、快適な旅ができるかが重要だと考えます。具体的には天候のことで、天気が悪ければせっかくの旅行も台無しになるからです。
私は高校時代、9月の連休に家族で沖縄に行ったのですが、予報よりも早く台風が到着して、ホテルに缶詰めになったことがあり、どこにも行けずに悲しい思いをしました。」
9、議論のまとめ
ここまでの議論を踏まえて結論をまとめます。
例題の場合は、③選択肢のうちより基準を満たしたものを選ぶ プロセスです。
今回は「北海道」と「沖縄」から、より多くの基準を満たした方を選びます。
10、発表
・どのような結論が出たか
・その結論に至るまでの議論の過程
簡潔にまとめて発表しましょう。
例)「私たちのグループでは北海道が新婚旅行の行先としてふさわしいという結論になりました。
今回、本州在住の25歳の会社員と専業主婦の夫婦が、11月に5日間旅行する前提で考え、更に北海道を札幌近郊、沖縄を那覇近郊と行先を限定しました。
快適な旅ができるかどうかということを基準にして選択肢を評価したところ、秋(9-10月)の沖縄は台風のリスクがあること、
JRや私鉄といった公共交通機関が発達していないことなど、天候や移動時間の観点から北海道のほうが快適な旅ができると考え、北海道のほうがふさわしいという結論になりました。」
グループディスカッションでどんな人が受かるにか気になりませんか?累計7万人の参加者の中で受かる人の特徴があることが気づいたので、合わせてご覧ください。
たった1日であなたのグルディス対策を完結させます

グループディスカッションに合格するには絶対に実践経験が必要です。
「出会いの場」に参加すると、以下のメリットがあります。
・1日15分×4回の実践による圧倒的練習量
・実際の人事の採点であなたの得意不得意と順位が分かる
・一度に最大14社と出会え、直接企業の本選考に進める
グルディス対策をしたい&1日で就活を大幅に進めたいという方はぜひご参加ください!
オンラインは何か流れが違うの?

コロナ禍の就職活動において、感染症対策の観点から、オンラインでのグループディスカッションが格段に増加しました。
対面(オフライン)のグルディスとオンラインのグルディスの違いについて説明します。
基本的には一緒
流れは基本的に一緒です。
自己紹介やアイスブレイクを行なって距離を縮め、役割分担と時間配分を行い、前提確認→プロセス設計→議論→議論のまとめ→発表…と進行していきます。
注意したいのは、カメラやマイクの設定、オンライン会議ツール(Zoom、Google Meetsなど)の設定など、対面グルディスにはない要素についてです。
グルディスの前に
・接続環境は問題ないか:途中で接続が切れたり、会議ツールが動作停止しないよう、Wi-Fiなどの電波状況を確認しましょう。
・カメラに画像(自分の顔)が映っているか:目線にも注意。画面ではなくカメラを見るようにしましょう。
・マイクが自分の声を拾っているか:事前にテストしておきましょう。
・相手の音声が聞こえるか:PCまたはスマホ本体の音量も確認しましょう。
ブレイクアウトルームに自分で行くものもある
Zoomではブレイクアウトルーム(分科会)という機能があり、メインルームに集合して少人数ずつブレイクアウトルームに振り分けられるケースもあります。
その際、企業が学生を移動させる場合もあれば、学生自身で指定のルームに移動する場合もあります。企業からの説明を聞き漏らさないように注意してください。
自分で移動する場合、メニューバーから「ブレイクアウトルーム」を選択すると、ブレイクアウトルームの一覧が表示されて移動が可能になります。
メニューバーから選べない場合はZoomのバージョンが古いことが考えられますので、常に最新版に更新しておきましょう。
ドキュメントの共有
オンライン会議ツールでは画面共有が可能です。
書記がメモ帳やWord等で記録を取り、それをリアルタイムで全員に共有することができます。うまく活用して議論に役立てましょう。
なお、オンラインでは微妙なタイムラグが発生します。
書記がメモを取り終える(あるいは、メモの入力が共有画面に反映される)のを待っているとタイムロスになるため、注意しましょう。
グループディスカッションが実際にどのような評価基準なのかを実際に使われている採点表を見せながら解説しています。
→グループディスカッションの評価基準は?採点表を公開しながら解説!
まとめ
グループディスカッション選考は、自己紹介、アイスブレイク、役割分担、時間配分、前提確認、プロセス設計、議論、まとめ、発表…という流れに沿って進行しますが
忘れてはならないのは
・まずはメンバー同士の距離を縮めて
・それぞれの得意分野を活かしながら
・より深い議論をして合意形成し、結論を導く
ということです。
周りをしっかり見て臨機応変に対応することが求められます。
オンラインの場合も基本的には同じ流れですが、オンラインならではの要素には注意するようにしてください。
この記事と併せて読みたいグループディスカッションの厳選記事
・ファシリテーターのコツ知りたい人におすすめ記事
・グループディスカッションで話せない人におすすめの記事
→グループディスカッションで話せない人でも内定が取れる具体的3STEP
・グループディスカッションのテーマを解く練習がしたい方はこちら