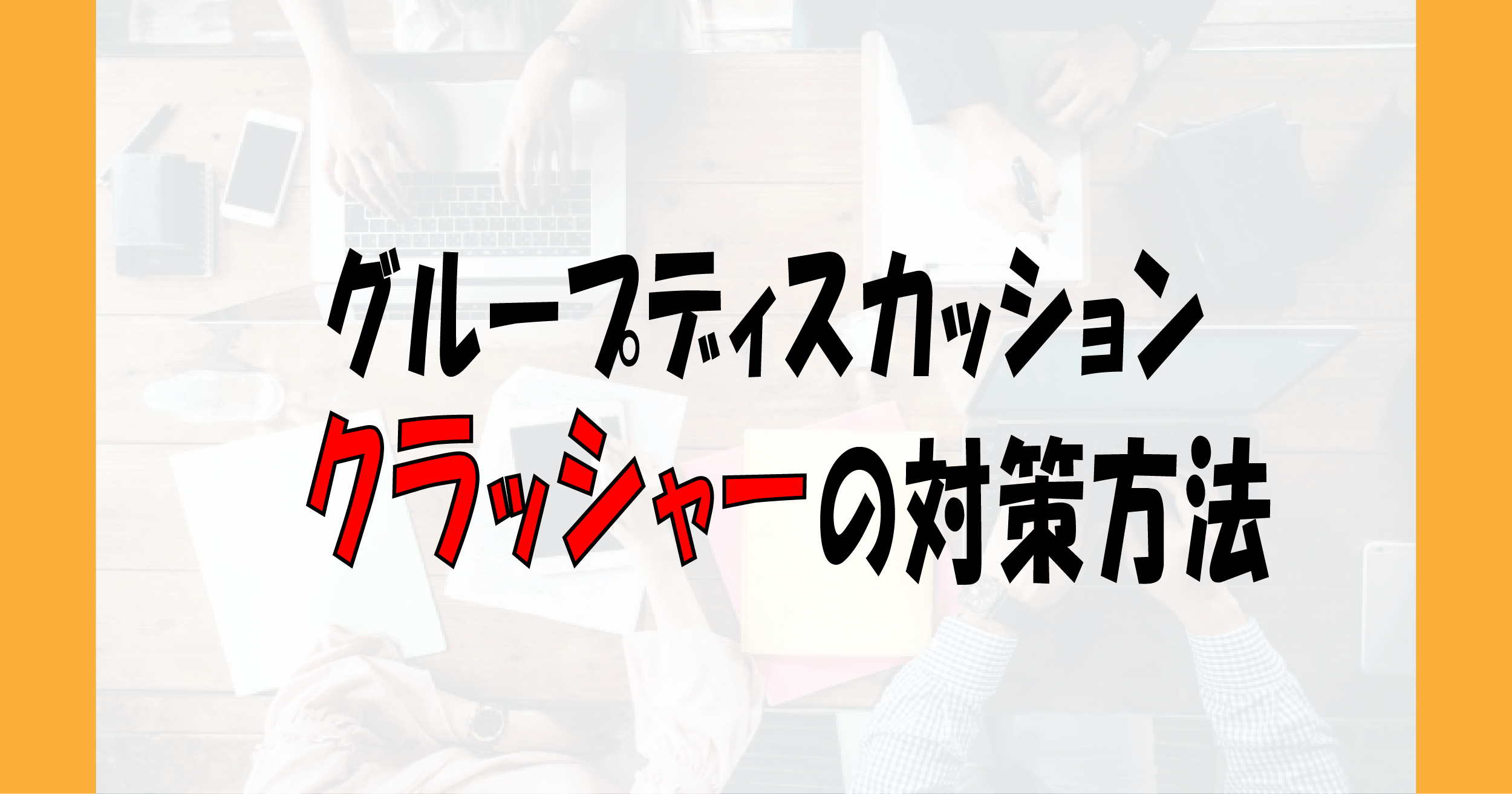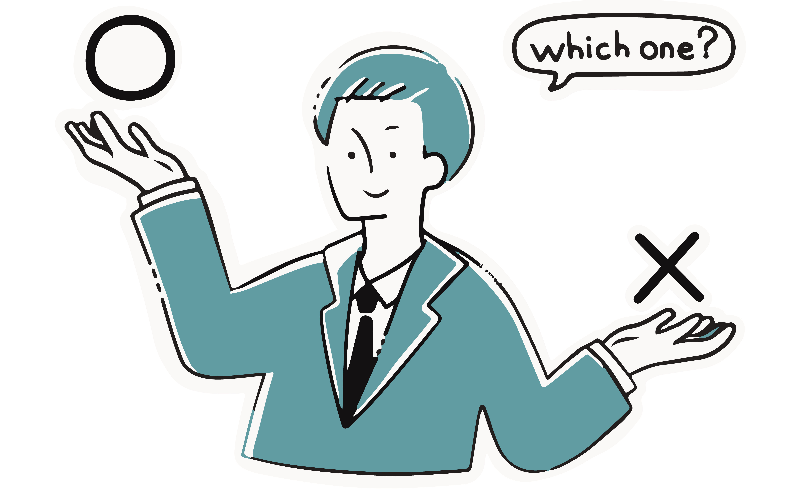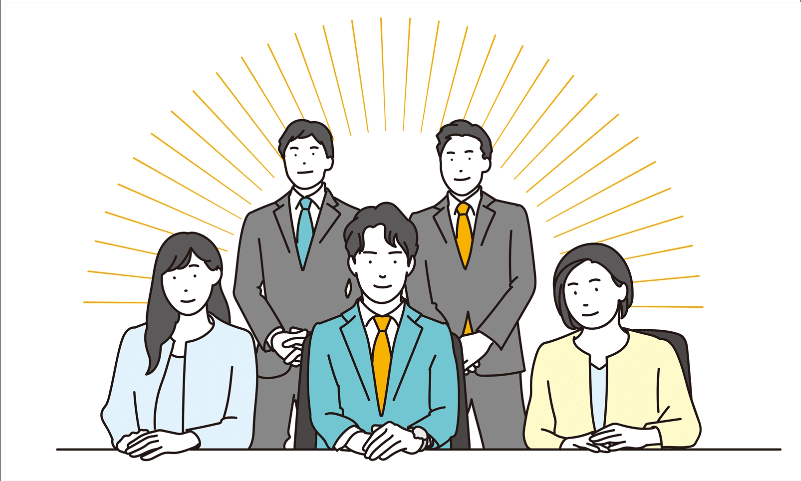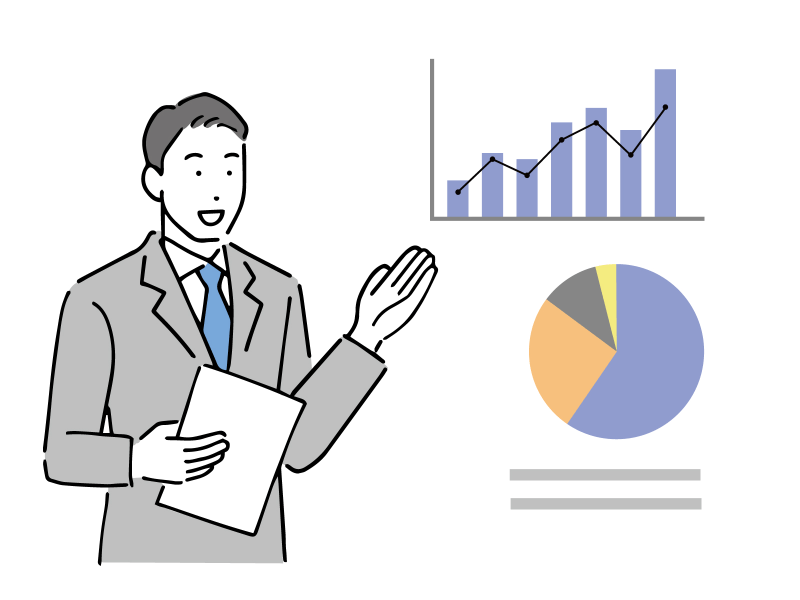グループディスカッションでクラッシャーに会ったことはありますか?
クラッシャーとはグループディスカッションの議論を妨げる存在という意味なのですが、実際にクラッシャーがいた際はグルディスの難易度が数段引き上げられます。
どんなメンバーが来るかは完全に運のため、もし最悪のメンバーだとしても対応できるように対策をしておかなければなりません。
なので今回はグループディスカッションでのクラッシャー対策として対処方法をタイプ別に超詳しく紹介していこうと思います。
クラッシャーって本当にいるの?
まず最初にクラッシャーって本当にいるの?というあまりグループディスカッションをやったことがない人のためにクラッシャーってどんな人のことで、
筆者が出会ったやばいクラッシャーの体験談を紹介していこうと思います。
クラッシャーってどんな人
クラッシャーとはグループディスカッションの議論の進行を阻害する人、違った方向に先導する人のことです。
要するに、議論を壊してしまう人のことを言います。
しかし実際には議論の進行を妨げる行為は程度の問題なので、あまりにひどい場合はクラッシャーと呼ばれますが、少なからず議論を妨害している人は高学歴な人でもいます。
クラッシャー実体験
実際に私が合ったクラッシャーは後ほど紹介しますが”的外れタイプ”のクラッシャーでした。
その方は、グループディスカッションが始まってすぐにファシリテータに立候補したものの、ファシリの役割が初めてだったのか焦っており、あまりスムーズな進行ができていませんでした。
そして進むべき方向をすっ飛ばし、線路を右折し違う方向へとみんなを誘導してしまうような方でした。
このようにクラッシャーは結構身近に存在します。
クラッシャーってどれくらいの割合で会う?
まだクラッシャーに出会ったことない人は先ほどの実体験に、「話盛りすぎでしょ」と思ってしまうかもしれませんが大体10回グループディスカッションを行ったら3回はクラッシャーと呼ばれる人に出会います。
なので33%の確率であなたも自分の大事な選考で会うことになります。
そのためそんなクラッシャーのために自分の大事な選考を落とすわけにもいかないので、クラッシャー対策をしなければなりません。
クラッシャーのタイプを紹介
では実際にクラッシャーにはどのようなタイプがいるのか紹介していきます。
クラッシャーの基本的なタイプは以下の7つになります。
・でしゃばりタイプ
・的外れタイプ
・否定タイプ
・無言タイプ
・時間搾取タイプ
・コンサル病タイプ
・短気タイプ
・発表下手タイプ
では1つ1つどのようなものクラッシャーなのか解説していきます。
でしゃばりタイプ
でしゃばりタイプとは自己主張が強く、喋りすぎてしまう人のことです。
これは皆さんも結構想像しやすいのではないでしょうか?
というのもでしゃばりタイプはグループディスカッションだけでなく、学校でも友達の中でもこのタイプは存在します。
このタイプは物事に熱中してしまい、視野が狭くなってあまり周りが見えなくなってしまうという傾向があります。
的外れタイプ
的外れタイプは先ほど説明した通り、テーマやその状況とは的外れな発言をしてしまい、チームをそちらに誘導してしまう人のことです。
このタイプの人は、今何をしているのかという状況観察力や思考力が低い傾向にあります。
的外れタイプとでしゃばりタイプが合わさると、とんでもないクラッシャーが誕生しグルディスの難易度が一段と上がります。
否定タイプ
否定タイプは、自分が正しいという思い込みが強く自分以外の意見をほとんど否定してくるような人のことです。
このタイプは自分に自信を持っているような高学歴の人に多い傾向があります。
グループで意見を出し合って、最終的にいいアウトプットを出すのがグループディスカッションなので、否定タイプも立派なクラッシャーになります。
短気タイプ
短気タイプは、自分の意見が上手くいかなかったり否定されたりした場合に怒ってしまう人のことです。
このタイプは先ほどと同様に自分に自信を持っているタイプに多い傾向があります。
否定タイプはなんとか自論を持って否定してきますが、短気タイプは反対意見に返せなくて怒ってきます。
無言タイプ
無言タイプはグループディスカッション中にほとんど喋らないタイプになります。
このタイプは人見知りでコミュ障の人であったり、あまり意見が出てこない思考力が低い傾向になります。
クラッシャーに中では議論そのものを邪魔するわけではありませんので、比較的マシな方になります。
ですがその人がいることで雰囲気を盛り上げにくくなったり、他の人まで伝染してしまうためクラッシャーにはなります。
時間搾取タイプ
時間搾取タイプは、議論の中で不必要な発言をして制限時間をどんどんと搾取してくる人のことです。
例えば、前提を超細かく決めるであったり、一度決まったところへ戻ろうとしたりなどの行動のことです。
このタイプの人は論理性が低い傾向があり、自分ではあまり気づいていないことが多いです。
コンサル病タイプ
コンサル病タイプは、難しい横文字やフレームワーク、分解ぐせなどがある人のことです。
フレームワークや横文字を正しく使うことは決して悪いことではありません。
悪いのはあまり意味が分かってないのに使ったり、正しく使えていないことです。
何より他の人があまり意味を知らない横文字やフレームワークを使いながら、議論を進めていくと、皆の認識がバラバラになり上手く噛み合わなくなります。
コンサル病の1つの対策としてフレームワークや難しいボキャブラリーを知っておく必要があります。
グループディスカッションでよく使われる言葉を難易度順に紹介しています。
発言の意味不明タイプ
発言意味不明タイプは、発言を聞いていても???が頭に浮かんでしまう人のことです。
このタイプは発言の基本がなっておらず、話が長い傾向になります。そのため議論の時間を奪われたり、議論のスピード感が落とされたりします。
たった1日であなたのグルディス対策を完結させます

グループディスカッションに合格するには絶対に実践経験が必要です。
「出会いの場」に参加すると、以下のメリットがあります。
・1日15分×4回の実践による圧倒的練習量
・実際の人事の採点であなたの得意不得意と順位が分かる
・一度に最大14社と出会え、直接企業の本選考に進める
グルディス対策をしたい&1日で就活を大幅に進めたいという方はぜひご参加ください!
グループディスカッションクラッシャータイプ別対処法

ではここからはクラッシャー別にどのように対応すればいいのか超詳しく紹介していきます。
解説方法として、クラッシャー別の特徴を並べ、その特徴だからこう対処すればいいという順番で紹介していきます。
クラッシャーの対処法といっていますが、クラッシャー自身を対処する場合もありますが、タイプによっては対処することができない場合もあります。
なのでここで紹介するのは、特定のクラッシャーのタイプがいても自分がグループディスカッション選考で通過する方法を紹介していきます。
でしゃばりタイプ
特徴
・目立とうとしている
・自尊心が高い
・あまり周りが見えていない
・発信力が強い
でしゃばりタイプはこのような特徴があります。
対処方法
その人の発言が進むべき方向に進めていて、正しい手順を辿っているかチェックしましょう。
これは頭のいいしゃばりすぎなのか頭の悪い喋りすぎなのかによって対象方法が全く変わってきます。
頭のいいでしゃばりタイプ
このタイプは間違った方向には進まないため、その人自身に何か対処する必要はありません。むしろ勝手に正しい方向に進めてくれるため便利です。
その場合は、サポート役に徹するようにしましょう。
つまり統率力で戦うのではなく協調性をアピールすることが頭のいいでしゃばりタイプがいた際の賢い戦略になります。
では具体的に協調性をアピールする方法を挙げていきます。
・話せてない人に話を振る
・クラッシャーの発言を分かりやすく要約してあげる
・意見をまとめてあげる
これらのことを的確に行うことで、あなたはほぼ確実にグルディスを通過することができます。
ですが注意点があります。
協調性をアピールしながら、最低限の自分の意見を発言するというのは行いましょう。
話せない人にふる、意見を要約する、意見をまとめるというのはどこにも自分の意見がありません。
なので自分はこう思ったという発言を根拠付きで紹介しましょう。
頭の悪いでしゃばりタイプ
頭の悪いでしゃばりタイプは、でしゃばり+的外れタイプなので対応が難しくなります。
このタイプのクラッシャーにメンバーが先導されて、誰もその人を止められずに悪いアウトプットを出した時は、みんな落ちる可能性があります。
なぜならその人を対処しなかった、議論を修正しなかったと思われるからです。
そんな頭の悪いでしゃばりの対応方法が3つあるので、紹介していきます。
1、間違った発言を適宜修正する
これはでしゃばっている人が正しい方向を外れた時に的確に指摘する方法です。
例えば、「○と○を前提で決めましょう」と言われた時に「○はいいと思うのですが、○は議論にそこまで関係ないので、×を決めましょう」という感じになります。
この方法が何がいいかというと、間違った発言をするクラッシャーと対比されるため、自分が思考力や論理性があると思われやすいためかなりおすすめです。
2、ファシリテーターを乗っ取る
この方法はリスクもあるので特定の時しか行わないでください。
その特定な時というのは、間違った発言を修正するだけでは方向修正ができない場合です。
というのもこのファシリテータの役割を乗っ取ったというのはクラッシャーの人も分かりますし、採点者も分かります。
なのでクラッシャーも不快になりますし、採点者にも敵対関係だと思われるかもしれません。
ですがどうしても軌道修正ができない場合はこの方法を取らないと、最悪なアウトプットを出してしまいどうせ落とされます。
なのでどうしてもの場合はファシリという役割を奪いましょう。
3、そもそもこのタイプにファシリテーターは任せない
そもそもこのタイプはファシリテーターにさせないように心がけましょう。
そんなん始まる前から無能か有能か分からないじゃんと思われるかもしれませんが、以下のチェックポイントに全て当てはまる人がいたら自分がファシリテーターに立候補しましょう。
・落ち着きがない
・自己紹介が下手
・でしゃばりそう
この3つは見ていたら分かります。この3つのタイプがいたら自分がファシリテーターにならないと最悪の未来になる可能性が高いです。
的外れタイプ
特徴
・思いついたらすぐ発言をする
・根拠が薄い
・思考力が弱い
的外れタイプにはこのような傾向があります。
対処方法
このようなタイプは、ファシリーテーターの役割を任せると大体が中途半端な感じの議論になってしまいます。
それはテーマの要点を押さえていないからです。
なのでこのようなタイプの対処法は要点を押さえ、議論の骨組みを作っていくことです。
分かりづらいので具体例を紹介していきます。
「どんな組織でも活躍できる社会人の特徴を3つ挙げろ」
このテーマが出た時に、「どんな組織」「活躍できる」の2つは定義の優先度が高く、「社会人」は軽く定義するかさらっと流しても大丈夫です。
このどこを定義するのかをファシリの人が下手に進行する前に提案しましょう。
次に解き方を提案しましょう。的外れな人がファシリをするとこの解いていく順番がめちゃくちゃになってしまうので、先に提案しておきます。
このテーマの場合は以下の手順で進めるのが定石です。
1、前提に乗っ取り活躍できる人材のアイデアを出し合う
2、判断軸を決定する
3、意見をまとめたり、判断軸に乗っ取って判断したりして3つに決める
このようにすることで、どんなファシリテーターでも簡単に進行ができるようになります。
結論として、定義するキーワード、解き方の流れを最初に提案するのが的外れタイプのクラッシャーの対処法になります。
否定タイプ
特徴
・自分が正しいと思っている
・協調性が高い
・瞬発力がある
・自分の正しいと思うこと以外は認めない
否定タイプはこのような特徴を持っています。
対処方法
このタイプの対処法は3ステップで考えてください。
1、相手の気持ちを逆撫でしないように発言する
否定タイプは自分の正しいこと以外も認めず、反対意見を言われたら「でも、いや」と反論してきます。
なのでできるだけ、相手を逆撫でしないように一度共感してから、反対意見を言ってみましょう。
例えば、「それいいね、でも○○だからこうじゃない」このように行えば比較的相手の否定モードに入ることなく反対意見をいえます。
2、味方をつける
基本的にこのような否定タイプの1対1の場合は、反対意見を言っても基本的には認めてくれることはありません。
なので1対2、1対3とこちら側の味方がつくと相手側も認めざを得なくなってきます。
1対1で戦うことはできるだけ避け、味方を作りましょう。
3、否定される前に他の人に振る
否定タイプは反対意見をいうと、すぐに「いや、でも」と言ってくるのは先ほど紹介しましたが、いやと言う前に他の人に振るというのはとても有効な手段です。
例えば「○というよりも×ではないと思うのですが、▲さんどう思いますか?」という感じで隙を与えずに他の人に振りましょう。
そうすることで、先ほどと同様に相手はこちらの意見に否定しにくくなります。
そしてこの3つを一緒にやることで、否定タイプのクラッシャーは否定をできなくなります。
例「確かに○○はいいと思うのですが、××だから▲▲の方がいいと思うんですけど、■■さんはどう思いますか?」
ここで自分の発言に賛同してくれると、ほぼクラッシャーは手も足も出ません。
グループディスカッションが実際にどのような評価基準なのかを実際に使われている採点表を見せながら解説しています。
→グループディスカッションの評価基準は?採点表を公開しながら解説!
短気タイプ
特徴
・自分が正しいと思っている
・単純に短気
・自尊心が高い
短気タイプにはこのような特徴があります。
対処法
この短気タイプは、先ほど紹介した一度賛成してから反対意見を言うというyes-but法を使いましょう。
よくyes-but法を使う人がいるのですが、形式だけ相手を一応褒めておこうという全然賛同していないのが見え見えの人がいます。
それでは全く効果はありませんので、本当に意見に賛同するように分かりますといい反対意見をさらっと言うようにしましょう。
そうすることで、短気の人の琴線に触れることはなくなると思います。
無言タイプ
特徴
・人見知り
・コミュ障
・思考力が低い
・緊張している
無言タイプにはこのような特徴があります。
対処方法
このような無言タイプは積極的に議論を邪魔しないため、いても対処をしなくてもいいです。
むしろこのタイプを対処することでアピールポイントになるぐらいの程度で考えてもらえて大丈夫です。
無言タイプの対処法は主に2つです。
1、最初から議論しやすいように雰囲気を作る
これはグループディスカッションが始まる前から勝負は始まってます。
まずは自己紹介です。別に笑いをとろうとしなくても大丈夫です。明るくハキハキ笑顔で話すようにしましょう。
そして結構重要なのが、挨拶ですね。こんにちはであったりよろしくお願いしますはどちらかは言うと思うので、こちらは一番最初に大きな声で言うようにしましょう。
2、簡単な質問を相手にふる
無言の人は基本的に人見知りで緊張している人が多いです。
なのでそのような人に自分の意見も求めるようなことはやめて、自分の意見を言って「〇〇さんはどう思いますか?」のような簡単な質問をしていきましょう。
プラスアルファで加点が欲しい場合はその静かな人が発言した時に「それいいっすね」のように褒めることで、その人はもっと発言しやすくなると思います。
時間搾取タイプ
特徴
・論理性がない
・状況が見えてない
・思考力がない
時間搾取タイプにはこのような特徴があります。
対処方法
時間搾取タイプは先が見えない人や今何をしているのか分からないという状況が分からない人に多いです。
このタイプには基本的には時間搾取をしようとした時にすぐに今議論しているところに戻すという手段を取るしかありません。
できるだけ時間搾取をしないようにさせるためには、議論の流れを最初に告知をする、定義を完璧にしておくというのが大事です。
そうすることで、「たぶんそれは次の段階だから今はこれを話そう」であったり「今定義を崩しちゃったらこれまでの過程がなくなっちゃうから」など修正しやすくなります。
ですが時間搾取をされているか判断するには、かなりのグループディスカッションを積まなければなりません。
なぜなら本当にそれが定義が必要か必要じゃないかというのは議論の先を読む必要があるからです。
なのでこの時間搾取タイプが実は一番多くて、一番対処が難しいクラッシャーになります。
コンサル病タイプ
特徴
・意識が高い
・コンサル志望
・周りが見えていない
コンサル病タイプはこのような特徴があります。
対処方法
コンサル病タイプは難しい横文字やフレームワークを使おうとしてくる人です。このような人の対処方法は主に2つです。
1、横文字やフレームワークを自衛用に覚えておく
自分が使うわけではなく、横文字を使う人がいた時に自分が議論に賛成していけるように最低限の横文字を覚えておく方がいいと思います。
そして横文字を使う人がいてもわざわざ突っ込まず、そのまま放置するようにしましょう。
2、他の人も分からなそうだったらその人に言って気づかせる
「すいません、さっきのMECEってどういう意味なんですか?」と素直に聞いてもいいと思います。なぜなら自分が分からない言葉は他の人も分からない場合があるからです。
それに一度そう言って牽制しておくことで、その人も気づいて難しい横文字を使わなくなる可能性があります。
なので自分以外もポカンとしていたら聞いてみるのは手の1つではあります。
発言意味不明タイプ
特徴
・論性性がない
・何か発言しないとと考え、勢いだけで発言している
発言意味不明タイプはこのような特徴があります。
対処方法
このタイプには、発言の基礎がなっていない場合が多いです。
発言の基本は”結論”→”理由”→”理由の補足”という形になっています。ですがこのタイプに多いのは理由→結論になってしまっています。
ではこのタイプの対処方法は3つあります。
1、推理力をあげ、つまり○○ってことですかと要約する
自分が分かりづらい場合は、ほとんどの人も同じように思っています。そんな曖昧な状態で話してしまうと、議論が間違った方向に進む可能性が高くなります。なので話が分からない場合はその人が何を伝えたかったのか察し、それを確認しましょう。
2、具体的に意見を言わす
人間は抽象的な発言よりも具体的な経験談の方が分かりやすかったりします。なので「具体的にどんな感じですか?」と質問すると、先ほどよりかは分かりやすく発言してくれます。
3、その人が発言しにくいようにする
どうしても発言の内容が分かりずらく、時間も搾取されるようであればその人が発言がしにくいように誘導していきましょう。
具体的な方法を2つ紹介します
・その人を観察し、話そうとした時に自分が話す
グループディスカッション中は熱中しており、そこまで観察してる人はいませんが、外からみていると発言したそうだなというのはとても分かります。それをディスカッション中に察して、その人が発言しそうなタイミングで自分が話し始めましょう。
・簡単なところだけ振る
グループディスカッションは基本的にでしゃばらないように心がけている人が多いです。なので発言が意味不明な人は簡単で誰でもわかるようなところで発言させるようにしましょう。
そうすることで自分の意見を言う時間を減らすことができます。
対処不可能なクラッシャー

クラッシャーの中に発表がとても下手なタイプというのがいます。
自分達が議論した内容とは違うことを発表したり、自分の意見を中心に発表したりします。
そのような人が発表すると、自分達の結論が悪かった感じでうつります。
ですが、このタイプは最初に役割を決定するので基本的には対処は不可能です。
ですがこのクラッシャーに対応する必要はありません。なぜなら採点者はずっと確認しており、発表が下手だなと本人が思われるだけで、チームメンバーのせいにはなりません。
なので発表が下手な人は対処しなくても大丈夫です。
面接はマナーを気にするのに、グループディスカッションではマナーを全く意識している人がいません。
そこでグループディスカッションでのマナーを紹介しているのであわせてご覧ください。
クラッシャーは実は得点源
ここまでクラッシャーの対処法を書いてきてクラッシャーに当たりたくないなと思っているかと思いますが、実はクラッシャーがいるのは実はラッキーだったりします。
理由は3つあります。
1つ目はクラッシャーというのは採点者も気づいており、その人をうまく対処するとコミュニケーション能力があるなと思われるからです。
2つ目はダメな人がいると、いい人が目立つからです。酸っぱいものを食べた後に、いちごを食べると甘く感じるような現象で、クラッシャーがマイナスアピールしているので、自分がちょっといいと目立つことができます。
3つ目は、ライバルが弱くなるからです。みんな実力がある人だと自分に求められる能力の水準も高くなりますが、クラッシャーは大体落ちますので、それだけ競争率は低くなります。
以上のことから自分にクラッシャーの対策法が確立している人は、クラッシャーがいた方がグループディスカッションの通過率は高かったりします。
自分がクラッシャーになる可能性は十分にある
ここまでクラッシャーに対応する側の解説してきましたが、実は自分がクラッシャーであるという可能性はめちゃくちゃあります。
例えば自分の発言によって議論がズレてしまい時間に間に合わないなどの場合は、採点者から見ると、あなたがクラッシャーと認定されてしまいます。
それにクラッシャーは0か100ではなく、どれくらいのところにいるかというもののため、テーマによってはあなたがクラッシャーになってしまうかもしれません。
自分がクラッシャーにならないために

では自分がクラッシャにならないためにどのようなことをすればいいのかというのを紹介していきます。
録画してみる
自分のグループディスカッションを録画してみるというのが一番分かりやすいです。録画しておくと、一回一回止めて自分の発言が良かったのか悪かったのかチェックすることもできます。
喋りすぎていないか、時間を奪っていないか、変な横文字を使っていないかを確認していきましょう。
録画はちょっとという方はグループディスカッションを録音しましょう。録音だとスマホのアプリでボタンを押すだけでいいのでおすすめです。
他の人に意見を聞く
他の人に意見を聞くというのも自分を客観的に知るいい方法になります。というのも、喋りすぎとか、高圧的とかは相手が判断するもので、自分の普通とは異なる場合があります。
なのでそのようなギャップを理解するためにも、他の人に自分の印象を聞くというのは有効な手段です。
グループディスカッションに慣れる
これは無言になってしまう人におすすめの方法になります。正直私はグループディスカッションは70%ぐらいは慣れによってカバーできると考えております。
ESや面接はこれまでの自分の人生のエピソードであったりを言わなければならないため、嘘をつかない限り、上限がかなり決まってきます。
それに比べてグループディスカッションは論理性やアイデアはこれまで築き上げた能力は必要ですが、でも慣れていない論理性がある人よりも論理性のない慣れている人の方が優れて見えることが多いです。
なので流れも理解できるし、アイデアも出しやすくなるため慣れるまでグループディスカッションを経験するのはとても重要です。
クラッシャーがなんで生まれてしまうの?
ここからはクラッシャーがなぜ誕生してしまうのかということについて紹介していきます。
選考だから
正直一番の理由は自分にとってとても大事な選考だからというのが一番の理由かなと思います。
選考だから目立とうとするし、競争の場であると捉えてしまって相手の意見をむやみやたらに否定したりしてしまう人が増えてしまいます。
なので選考だからこそみんなと協力して、落ち着いて望む必要があります。
時間制限がある
時間制限があることも、クラッシャーを生む1つの要因となっています。
グループディスカッションは短い場合15分ぐらいで行わせる企業もあります。そのような場合に焦って質の悪い発言をして余計に時間を無駄にしている人が多くいます。
なので自分の発言が間違っていないか、質は大丈夫かを気にしながら発言することがとても重要になります。
議論についていけない
クラッシャーを誕生させる1つの理由として議論についていけないというものがあります。議論についていけないというのは大体は慣れによって解決できます。
なのでグループディスカッションのイベントなどに参加するか、openchatなどで練習しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回はグループディスカッションでクラッシャーに遭遇した時の対処法を紹介していきました。
その対処法を習得することができれば、クラッシャーは得点源だと思えるようになってきます。
なので今回紹介したクラッシャー対処法を何度も見直しましょう。
そして自分がクラッシャーにならないために録画して、客観的に自分を見て確認してみてください。
この記事と併せて読みたいグループディスカッションの厳選記事
・グループディスカッションの絶対に受かりたい人におすすめの記事
・グループディスカッションの練習方法ってなにがあるの?という方におすすめの記事
・ファシリテーターのコツ知りたい人におすすめ記事