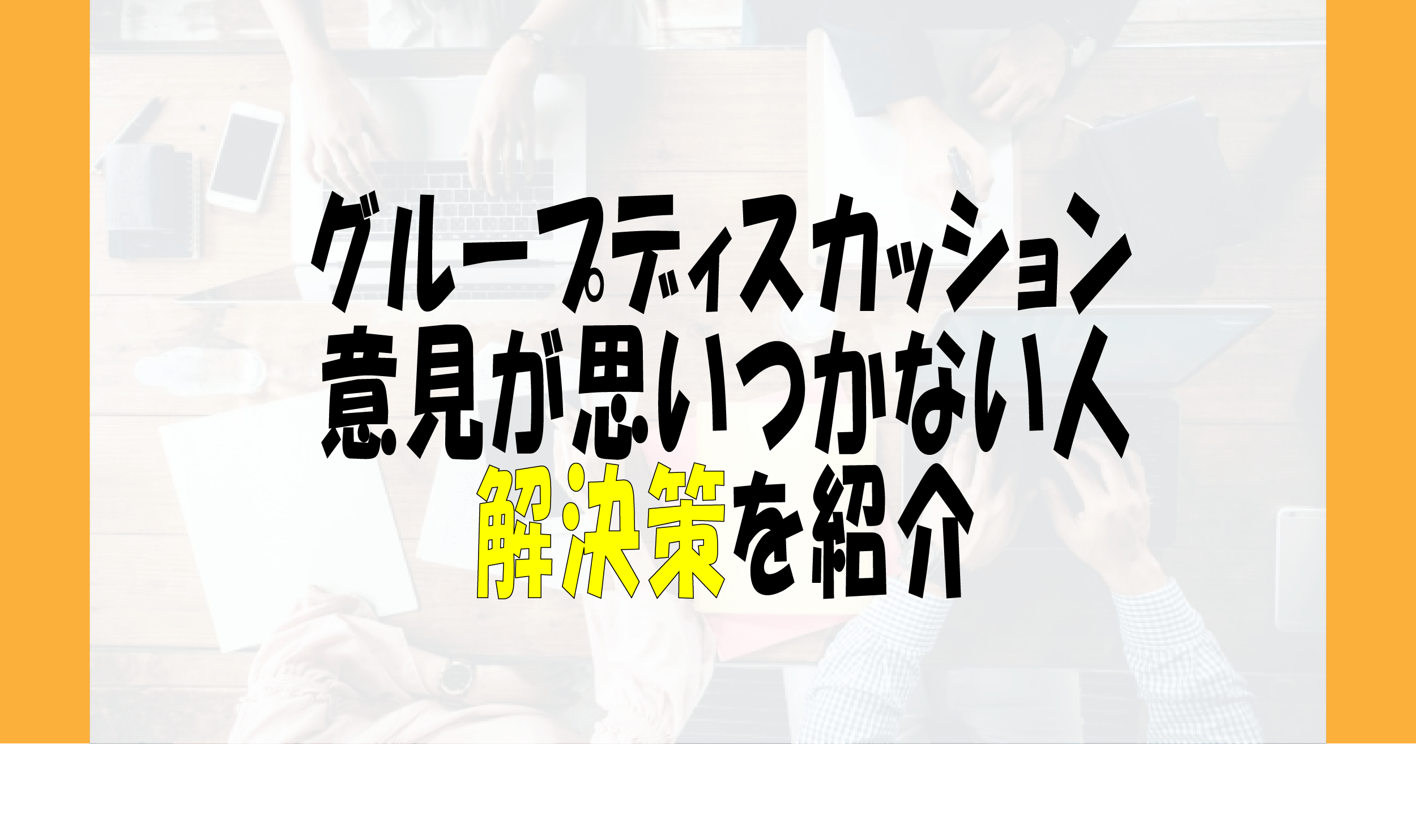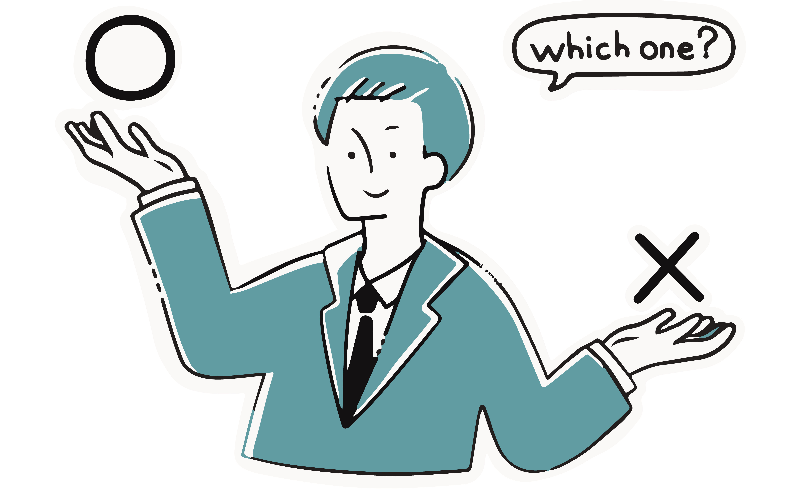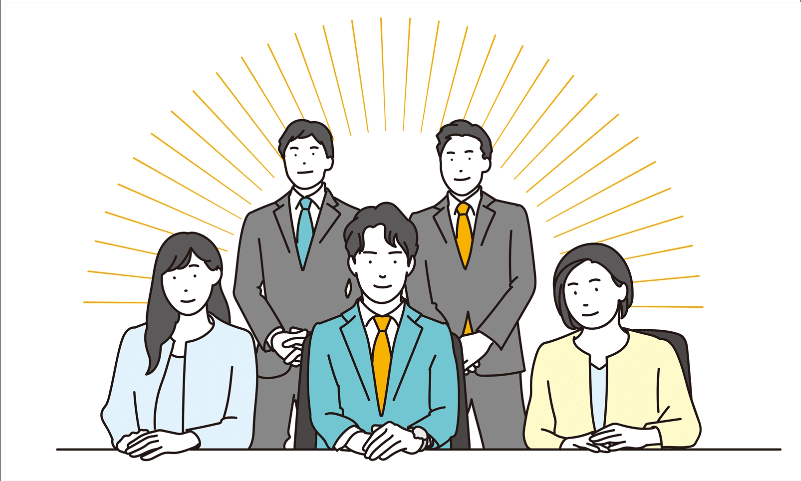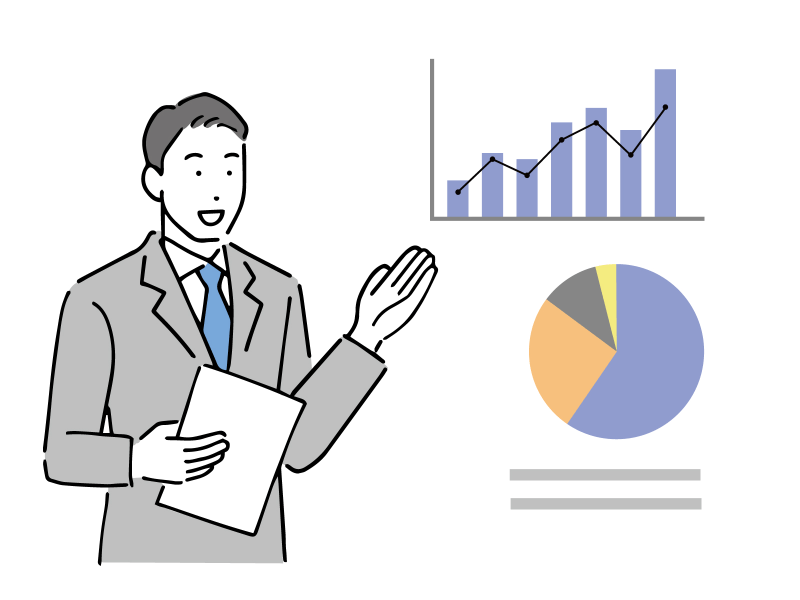グループディスカッションで意見が思いつかない方は多いですよね。
やはり自分で意見を持ってそれを言うことは以外とできないことが多く、そうなるとどうしても同調ばかりになってしまいます。
この自分の意見を持つと言うのは日常的にやってないと難しいところが多いですが、グループディスカッションに関しては、フレームワークやコツで意見を出しやすくすることができます。
なので今回はグループディスカッションで意見が思いつかない方が内定する方法について紹介していこうと思います。
グループディスカッションで意見が思い付かないのはなんで?
ではそもそもなぜ自分の意見を思いつかないのかいくつかのパターンを紹介していきます。
慣れが足りない?
「グルディスが苦手」「何を言えばいいか分からない」という人は、そもそも経験不足でグルディスに慣れていないことがほとんど。まずは場数を踏みましょう。
・インターン選考や早期選考にチャレンジ
・グルディスのイベントに参加
・グルディス練習会に参加
練習会は有志(学生同士など)で随時開催されているものが多く、twitterやオープンチャットでも参加者を募っています。
中には見学者を募集しているケースもあります。
そもそもグルディス選考のイメージがつかない!という人は、実践の前にまず見学してみて、雰囲気を掴むのが良いでしょう。
グループディスカッションが実際にどのような評価基準なのかを実際に使われている採点表を見せながら解説しています。
→グループディスカッションの評価基準は?採点表を公開しながら解説!
自分の意見を出しやすくするフレームワーク
グルディスで発言するためには、自分の考えを議論のいち意見としてまとめなければいけません。
単に自分の思ったことを話すだけでは、とりとめのない発言になって議論が滞り、いわゆる「クラッシャー」になってしまう可能性も。
グルディスでは「抜けなく、漏れなく」が大原則。フレームワークを意識すると考えやすくなります。フレームワークとは、共通して用いることのできる考え方や、意思決定の構造のことを言います。
5W1H法
5W1Hとは、Who(だれが)、When(いつ)、Where(どこで)、What(なにを)、Why(なぜ)、How(どのように)のこと。
それぞれの要素について考えることで、抜け漏れなく検討することが可能です。
3C分析
3CとはCustomer(市場環境)、Company(自社環境)、Competitor(競合環境)のこと。
これらの3要素を検討することで内部・外部の環境を抜け漏れなく洗い出すことが可能です。
このようにペアを考えると抜け漏れがなくなります(3Cの場合はトリオ)。
AIDMA
Attention(認知)→Interest(興味)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(購買)。
人が製品を認知してから購買するまでの動きのことで、アイドマの法則と呼ばれます。
このようにフローで考えると抜け漏れがなくなります。
パターンを理解するまで問題を解く
実はグルディス選考はパターンが決まっています。
勘の良い人は「なんだか似た問題ばかりだな」と気がつくことと思います。
問題を見た瞬間に「この問題は〇〇型だ」と分かるようになれば、おのずと解き方の道筋が見え、意見を述べることができるようになります。
グルディス選考は、大きく分類すると、以下の4つに分けられます。
・抽象型(定義型):抽象的なものや不明瞭なものを具体的な言葉で定義する
例)就活生にとって理想的な「スマートフォンのアプリ」を考えてください。
・選択型:複数の選択肢からふさわしい回答を絞り込む
例)都会と田舎のどちらに生まれたほうが幸せか検討してください。
・課題解決型:課題を解決するための策を考える
例)ボールペンの売上を上げる方法を検討してください。
・フェルミ推定:実際に調査することが難しい量を論理的に推論して概算する
例)日本に消防署が何件あるか検討してください。
中でも特によく出題されるのは、抽象型の「新規事業立案の問題」と、課題解決型の「売上や販売を上げる問題」です。
あらかじめ頻出問題の解法パターンを確認しておき、実践経験を積みましょう。
コンサル志望の人はフェルミ推定も必ずチェックしておいてくださいね。
面接はマナーを気にするのに、グループディスカッションではマナーを全く意識している人がいません。
そこでグループディスカッションでのマナーを紹介しているのであわせてご覧ください。
自分の意見を持つには

繰り返しになりますが、最も効果的なグルディス対策は「パターンを覚えて実践すること」。
自分の意見を出せない一番の原因は「経験不足」ですから、とにかく場数を踏むのが効果的です。
斬新な意見を出そうとしていないか?
「グルディスは何回か経験したけれど、やっぱりうまく話せない」「いつも何を言えばいいのか分からない」という人は、斬新な意見を出そうとしていませんか?
斬新な発言は、ユニークさで議論を盛り上げ、評価者にも鮮烈な印象を残すでしょう。
ですが、グルディスでの発言は、斬新さや目新しさ、ユニークさだけが評価されるわけではありません。
あくまで自分の考えを素直に述べることがポイントです。
ただ、一般論や常識を並べただけでは、議論は前に進まず、評価者の印象にも残りません。
そこで、「私はこう思う」という意見を、自分自身の経験によって理由づけするようにしてみてください。
例)「恋人との記念日には、ちょっと特別な食事をするのが良いと思います。お祝いなのだから、普通はそうしますよね。」
→「恋人との記念日には、ちょっと特別な食事をするのが良いと思います。私も恋人と付き合って半年の記念日に、ホテルのレストランでお祝いをしましたが、いつもと違う雰囲気で、特別な思い出になりました。」
たった1日であなたのグルディス対策を完結させます

グループディスカッションに合格するには絶対に実践経験が必要です。
「出会いの場」に参加すると、以下のメリットがあります。
・1日15分×4回の実践による圧倒的練習量
・実際の人事の採点であなたの得意不得意と順位が分かる
・一度に最大14社と出会え、直接企業の本選考に進める
グルディス対策をしたい&1日で就活を大幅に進めたいという方はぜひご参加ください!
自分の意見を言わなくても評価は得られる
グルディス選考では、主に以下のような要素が見られています。
・発言力:積極的に発言しているか、発言の質はどうか
・統率力:メンバーをうまくまとめられているか、議論をうまく進行できているか
・協調性:メンバーと関係構築できているか、メンバーの意見を引き出せているか
・論理性:論理的に考え、論理的に議論できているか
自分の意見を出せるかどうかというのは、「発言力」の部分。
具体的には、積極的に発言できているか、その内容の質はどうか(説得力のある意見で議論を進めることができたか、意見に独自性があったか)、等の評価がなされています。
ここで誤解してはならないことがあります。
グループディスカッションのゴールは「全員で合意形成して結論を導くこと」であって、必ずしも「ユニークな発言をすること」とイコールにはなりません。
どうしても自分の意見を出せない人、自分の意見に自信を持てない人は、ほかの要素で加点を狙うのも1つの手。
独自性やアイデア力の評価は低くなりますが、総合評価が高ければ選考には通過できます。
・意見を聞きながらまとめを考えておく
他メンバーの発言を聞きながら、要所要所でそれまでに出た意見を総括したり、最終的な結論にまとめてみるのも手です。
・考えなくていい部分だけ発言する
「まず前提を定義しましょう」「原因を深掘りしましょう」など、パターン化した中で議論の方向性を提示する。
・決まったセリフを言う
「まず前提を定義しましょう」、「次に議論の流れを設計しましょう」など、「これだけは発言する!」というものを決めておく。
・・・等々ですが、「どのタイミングでどんな発言をすればいい?」というのは、やはり経験則。
とにかく場数を踏んで慣れることが一番の選考対策です。
まとめ
グルディスに苦手意識のある人は、「何を言えば分からない!」という人も多いでしょう。
もちろんユニークな意見を出すことができれば言うことなしですが、グルディス選考では発言力以外の要素も評価されています。
「どうしても何を言えばいいのか分からない!」という人は、発言力以外の要素に振り切るのも手といえます。
ですが、まずは場数を踏んでグルディスに慣れることが重要です。
この記事と併せて読みたいグループディスカッションの厳選記事
・グループディスカッションの絶対に受かりたい人におすすめの記事
・グループディスカッションで話せない人におすすめの記事